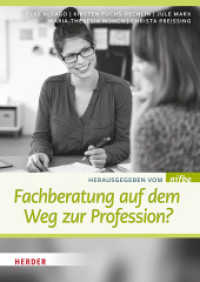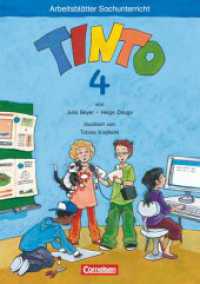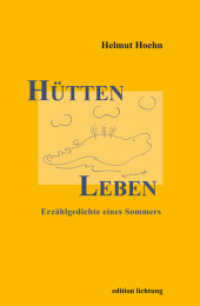内容説明
地名はある日突然、何の脈絡もなく出現するものではない。誕生し受け継がれていく必然性が、必ずある。その地の人々の営みや文化の継承、神話や伝説など、そこには土地に刻まれた様々なドラマが秘められているのだ。古今東西の地名の由来を読み解き、その本来の意味を探ってゆく。
目次
1章 アジアの地名の起源―世界最大の大陸を舞台に地名はどう生まれ、どう旅したか
2章 中東・アフリカの地名の起源―中東「スタン」地名の由来から、アフリカ地名と欧州との関係まで
3章 ヨーロッパの地名の起源―ケルト、ゲルマン、スラブ…地名から民族と国家の活動が見えてくる
4章 アメリカの地名の起源―大航海時代、開拓時代の地名から新興大陸ならではの地名文化を読む
5章 オセアニアの地名の起源―“幻の大陸”命名までの歴史から、ハワイに残る地名伝説まで
6章 世界全般の地名の起源―民族国名、河川名、神話地名…こうして地名は誕生した
著者等紹介
辻原康夫[ツジハラヤスオ]
1948年、広島県生まれ。明治大学文学部史学地理学科卒業。数年間の海外放浪の後、旅行雑誌記者、書籍編集者などを経て、85年から情報編纂のシンクタンク「見聞録」を主宰。地誌研究家、ノンフィクションライターとしても、世界と日本の地誌、生活地理、国際関係論、地名研究、旅行文化など多岐にわたる分野で活躍している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
29
2001年刊。話題豊富だけど正確さはほどほどらしい。以下メモ。⚫︎ケルト語のブリガ(高台)は町の名に残る。ドイツ語圏はブルク(ハンブルク等)、フランス語圏はブール(シェルブール等)、スウェーデンはボリ・ボー(イエーテボリ等)、英語圏はバラ・ベリー・バーグ(エディンバラ、カンタベリー、ピッツバーグ等)。⚫︎フランク王国等に攫われ売られたスラブ人は、英語slave=奴隷、serve=勤める、service=客への対応、の語源。スラブ人の地=ユーゴスラビア・セルビア。⚫︎ケルト語でゲルマンとは「騒々しい人」。2025/02/16
TAKAMI
0
「集落」を意味する「プル」語群の世界への広がりとか、とても興味深く読めました。ハワイの地名が一時期サンドイッチだったとは…2014/08/16