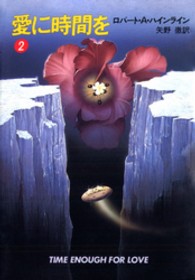内容説明
快適を求めた生活大革命時代。近代都市生活の成立過程の中に、豊かさへの夢と現実の矛盾構造を詳細具体的に描く。
目次
現代社会の夜明け―石炭と鉄と勤勉
コーヒー文化の誕生―生活様式の国際化
多彩化する生活
人口過密・異臭・貧困―都市の生活環境
庶民生活の哀歓
食事・娯楽・旅行―庶民生活の向上
虚栄の市―上流・中流階級の生活
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふろず
3
産業革命期のイギリス民衆生活史。執筆からかなり経っているためか、所々出てくる例えが古くなっている。しかし本書は当時のイギリス人を知るために日本語で書かれたものとしては外せないと思う。こういう良書から興味は派生していくものだ。生活史は面白い。2023/06/26
maqiso
1
産業革命期のイギリスでは工業化や輸入品の増加や大都市の出現によって庶民の生活が大きく変わった。茶は初めは高価な薬であったが急速に普及した。ロンドンと上の階級への憧れによって、新たな文化がイギリス中に広まる。都市は上下水道が貧弱で悪臭が立ちこめ、下層階級は不衛生な中で早死にする。まとまりはないが個々の話は面白い。2020/11/11
diet8
1
面白い。産業革命期(18,19世紀)の英国の生活史。 ●1802 1833 工場法が英国教育のはじめ。徒弟期間の最初の四年で教育を工場主に定めた ●著者が1963年日曜に下宿で掃除機かけたら怒られた ●日曜が休日になったのは宗教改革以降、17世紀に一般的になった。土曜半ドンは19世紀中頃 ●狐狩りの名手はプロ野球選手並みの国民的英雄だった。鉄公爵ウェリントンが狐狩りの大将軍と呼んだアシュトンスミス1776-1856+ ●初等教育がはじまったのは1870年から。それまで家庭教師や個人経営の学校でしていた 2017/09/04
富士さん
1
再読。時代全体の経済の動きから個人の家計簿、時代のエートスから一時的な流行、歴史的な事件から一般人の日常のエピソードまで、ミクロからマクロまでに広く目を向け、一冊の本にうまい具合にまとめられており、個人的には本書を生活史記述の雛形にすべきだと思うほどの完成度です。この時代が生活史記述に適した時代だということもあるとは思いますが、それでも着眼点と構成の完成度は見事であると思うのです。他の時代もこのような記述を目指して資料を収集し、各論の研究を進めていけばより魅力的な歴史が立ち現れてくるに違いありません。2015/09/25
ぼけみあん@ARIA6人娘さんが好き
1
角山氏の産業革命に関する著書を読んでみたいと思って手に取った。産業革命の推移などの細かい推移ではなく、産業革命期のイギリスの労働者を含む民衆の生活史に関して書かれた本。当時のロンドンの状況や労働者の置かれたかなりひどい状況などもよく書かれている。あの状況を見ては、マルクスならずとも資本主義先進国で革命が起こると予言して当然だろう。ちょっと古い本だけど、生活史に関しては草分け的な本らしく、色々と勉強になる。なお余談ながら、弟子の川北氏は元々そのような庶民的な視点を持っていなかったようだ。2012/01/12