内容説明
シーモア・グラースが語る、バナナフィッシュの悲しい生態(「バナナフィッシュ日和」)、少年たちが夢中になる笑い男の数奇な冒険(「笑い男」)、兵士に宛てられた小さな淑女からの一通の手紙(「エズメに、愛と悲惨をこめて」)。現実を綱渡りで生きるひとびとの一瞬を切り取った、アメリカ文学史上に輝く自選作品集。
著者等紹介
サリンジャー,J.D.[サリンジャー,J.D.] [Salinger,Jerome David]
1919年、アメリカ・ニューヨーク生まれ。40年に短篇「若者たち」でデビュー。42年、陸軍に入隊しノルマンディー上陸作戦に参加。51年に刊行した長篇小説『キャッチャー・イン・ザ・ライ』が全世界で大ベストセラーとなる。53年に『ナイン・ストーリーズ』を刊行後、ニューハンプシャー州で隠遁生活をおくった。2010年没
柴田元幸[シバタモトユキ]
1954年、東京生まれ。アメリカ文学研究者、東京大学名誉教授。翻訳家。著書に『生半可な學者』(講談社エッセイ賞)、『アメカリン・ナルシス』(サントリー文芸賞)など。訳書にトマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』(日本翻訳文化賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tonpie
53
印象のみ。高次の次元を求める神秘主義の傾向がある。 主要人物も作者自身も「純粋さ」「高み」を求めているので、読んでいて非常に疲れる。 「哀切さ」の印象も大きい。それは、純粋さを志向する人が、それにふさわしい対応を受けず、何かに埋もれてゆくことの哀しみ。↓2025/05/07
けぴ
45
『本当の翻訳の話をしよう 』を読んで翻訳家の柴田元幸を知る。この著書の中で語られていた『ナイン・ストーリーズ』を柴田元幸訳で読む。原著をなるべく忠実に訳すように心掛けているそうです。「エルキモーとの戦争前夜」で、Did you eat yet? (もう食べた?)が前歯のあいだにはさまった食べかすをほじりながら喋ることでJeat jet? となっているのを(おうはへは?)と訳していた箇所は名人芸でした。ストーリーとして一番おすすめは「ド・ドーミエ=スミスの青の時代」日本人夫婦の開く絵画教室を舞台にした笑話。2024/06/02
ワッピー
36
若い方からおススメを受けて、40年ぶりに再読。今回は柴田元幸さんの訳ということで、当時感じた「不条理感」が解消するかと思うも、そこはそのまま作品の心臓部でした。死の渇仰、不毛なる回顧や打算、子どもたちのヒーロー、母と子の駆け引き、年若い淑女との邂逅、妻の不倫恐怖、絵画指導や神童をテーマに、徹底的に常識とのズレを意識させる9つの作品ですが、初読当時よりは余計な知識と少しの経験を積んだことにより、異質感ではなく自分ももう少しでこの域に到達できるかも、という恐れを感じました。そう、まだ3歩ぐらい先かな・・・。2024/01/17
特盛
35
評価4/5。サリンジャーの短篇集。ライムギ畑と同様、「子供の世界はあんなに美しく素晴らしいのに、どうして我々は大人になると汚れつまらなくなってしまうのか」ってテーマを一貫して作品に感じる。そしてそれはオッサンには悲しい。本作収録作品の中では、「エズメに、愛と悲惨を込めて」が実に村上春樹的雰囲気で大好きだ。いや、村上春樹の中のサリンジャー的雰囲気に触れられるというか。9作品とも、たまにまた見返したいなと思う。どれも素敵な空気を纏った作品だった。柴田元幸訳で読めたのもよかった。2025/05/24
n.k
27
良くも悪くもくどくど。集中しないと話が頭に入ってこない難しい本。でも、不思議と情景がはっきり目に浮かぶ。何言っているかわからず歯がゆい気分にもなるが、ふとしっくりくる言い回しもある。見栄を張る男の描写と、年頃の子供の異常性の描写がコミカルでとてもよい。2025/01/08
-

- 電子書籍
- 俺の背徳メシをおねだりせずにいられない…
-

- 電子書籍
- 隠れ星は心を繋いで~婚約を解消した後の…
-
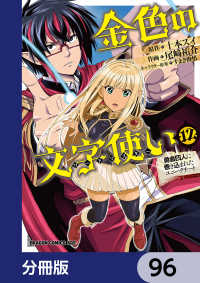
- 電子書籍
- 金色の文字使い ―勇者四人に巻き込まれ…
-

- 電子書籍
- ペリーさんちの、おきらく貧乏ごはん(分…





