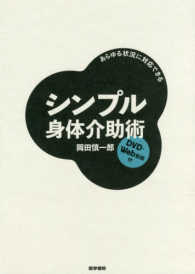内容説明
人肉食、ゾンビ、神童による宇宙図鑑、中華マジックリアリズムの代表作、中国のシェイクスピアによる短編、イギリス人実業家が刊行した石版印刷の画報、そして『阿Q正伝』まで。怪談の概念を超越した他に類を見ない圧倒的奇書が今よみがえる!中国の真髄に触れる、かつてない異色のアンソロジー!
著者等紹介
中野美代子[ナカノミヨコ]
1933年生まれ。北海道大学卒。北海道大学名誉教授
武田雅哉[タケダマサヤ]
1958年生まれ。北海道大学卒。北海道大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
68
中国の怪談アンソロジー。編者二人の力量が只事じゃない。狭義の怪談こそあまり収録されてい無いものの、文字通り人を喰った話から始まり、悲惨を極める占領下の記録にサルマナザールの記録、新聞記事から「阿Q正伝」果ては天安門事件の「公式」報道と、虚実が入り混じり、現実幻想の皮膜は破れ、互いが互いを侵食したようなそんな話ばかり。読んでいるうちに茫漠としてきて、何となく中国を感じられるような気さえする。一番恐ろしいのは「北京で発生した反革命暴乱の真相」だけど、サルマナザールや「宇宙山海経」等壮大な法螺話もまたいいな。2020/03/16
k5
57
編者あとがきにも書いてありますが、怪談集だと思って読むとがっかりする一冊。しかし文学アンソロジーとしてはレベル高く、トリッキーな感じはスタニスワフ・レムに匹敵するのではという感じです。一読の甲斐はあります。あくまで怪談を期待するとガッカリしますが。2023/10/21
そふぃあ
27
収められているのはいわゆる”怪談”ではない。思わず唸ってしまう傑作もあり、最後まで読むのを拒みたくなる作品もあったのが個人的な感想。一筋縄ではいかない多彩な奇譚集。個人ではどうにもできない大きなシステムにおける弱者の選択や振る舞いに焦点が当たる作品たちが鮮烈で印象に残る。特に「揚州十日記」は肝が冷えた。(この後に読んだケン・ リュウの「草を結びて環を銜えん」が同じ揚州十日を扱っていて感慨深かった。)最後を飾るのが天安門事件に関する中国共産党の見解というのも恐ろしい皮肉。魯迅は初めて読んだが面白かった。2021/01/23
one_shot
13
半村良の「能登怪異譚」なんかが大好きな怪談アウトサイダーには垂涎のアンソロジーではないだろか。ストレートに人肉食を扱った「人を喰った話」から始まり魯迅の「阿Q正伝」(なぜっ⁈)そして掉尾を飾るのは天安門の真実として書かれた当時の人民日報の大本営記事「北京で発生した反革命暴乱の真相」。どの短編も奇妙な味があり捨てがたい逸品揃いだ。しかし、一番恐ろしいのは「恐怖」という通念に牙を剥く編纂者二人の狂いっぷりかもしれない。2020/03/19
圓子
13
『怪談』でこのラインナップおそれいる。縛りもなく枠もなく、まさしく怪しき談りばかり。カニバリズム趣味はないけれど、たぶん。それら文字列を目にすると手に取らずにおれない『人肉を食う』。これが一本目にあることで購入決定。電波系も時代を経ればファンタジー『台湾の言語について』『宇宙山海経』ゆかいゆかい。『五人の娘と一本の縄』とソフィア・コッポラのヴァージン・スーサイズに関係はあるのかないのか。乙女の純真と厭世は洋の東西問わず仄暗い憧れを象徴するテーマなのだろうね。好きよ。2019/12/21
-
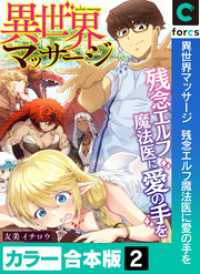
- 電子書籍
- 【カラー合本版】異世界マッサージ 残念…