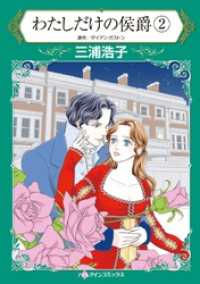出版社内容情報
フーコーが1970年におこなった講義録。『言語表現の秩序』を没後30年を期して40年ぶりに新訳。言説分析から権力分析への転換
【著者紹介】
1926~84年。20世紀後半における最も重要な思想家。著書『狂気の歴史』『言葉と物』『知の考古学』『監獄の誕生』『知への意志』『自己への配慮』『快楽の活用』など。
内容説明
没後三十年、フーコーの思想の画期となったコレージュ・ド・フランス開講講義『言語表現の秩序』を四十二年ぶりに気鋭が新訳。六十年代の知の考古学から七十年代の権力分析への転換を予示しつつ、言説の領界を権力の領界へと開くことで、その後の思想と政治に大きな影響を与えた名著。
目次
言説の領界 コレージュ・ド・フランス開講講義
訳注
解題 『言説の領界』を読む(慎改康之)
著者等紹介
フーコー,ミシェル[フーコー,ミシェル] [Foucault,Michel]
1926‐1984年。二十世紀後半における最も重要な思想家
慎改康之[シンカイヤスユキ]
1966年生まれ。明治学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
65
初めてフーコーにチャレンジしたが、言っていることが観念的過ぎるのとわたしの理解力を超えているところが多すぎた。もっとわかりやすい具体例を……。2019/09/10
ころこ
34
「フーコーコレクション」で講義が手に入るようになった現在で、60年代の主著と講義の蝶番の役割をするのが本書です。記念講義ですが平易ではありません。西洋におけるロゴスのシステムがテーマです。フーコーは言説の産出の管理として排除、制限、占有があるのは、いっけんロゴス愛にある西洋の言説に密かな恐れを感じるロゴス嫌悪が隠れているといいます。そうした恐れを消し去ろうとする言説管理の手続きがどの様になされるのかを批判し、別の場所に移すことで言説の秘密を明らかにする、考古学といわれる思想史研究の方法を展望しています。2018/11/02
evifrei
20
今までフーコーの入門書的な書籍は読んだ事があったが、フーコー自身のテキストにあたったのは恐らく初めてだ。言説には不安を伴うことを指摘した上で、言説の産出を管理するための手続きとして『排除・制限・占有』があることを述べた前半部分と、そうした管理のもとで形成されるものとしての言説を如何にして分析すべきかを検討する後半部分からなる。フーコーが担当した講義の開講講義の記録という本書の性質上文体は読みやすいのだが、内容を抽出するのは結構骨が折れる。概念が立ち上がってくるまでは掴めそうで掴めない感覚を受けた。2020/06/13
ドン•マルロー
18
言説の領界へようこそ。どうぞ、こちらへ。出口はありませんがね。少なくともあなたがたのように聡明な人、言説をあたかも松明のように振りかざして、領界だの出口だのとあくせく探し回るものどもにはね…2018/08/19
Z
12
『知の考古学』を代用できるかなと思ったが、やっぱり『考古学』よまないとだめだった。言説の定義がなされない。ある程度統一性を持った(理論)等の組織くらいにとらえると、それをもの、制度等を通して支える外的な編成方式と、言説の総合性を整える言説内部での編成方式に二分できる。外的要因として、排除の原理として、タブー、分割(ex健康/狂気に分ける精神医学)真理への意志(何が重要で何が重要じゃないか、教育、学会、実験室等、機関によう分割)をあげ、内的要因として、注釈(オリジナルとみなしうる原典とその解釈というレベルの2016/09/05