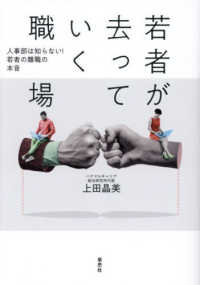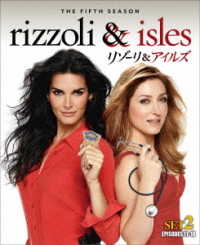内容説明
ナチスのユダヤ人虐殺を筆頭に、組織に属する人はその組織の命令とあらば、通常は考えられない残酷なことをやってしまう。権威に服従する際の人間の心理を科学的に検証するために、前代未聞の実験が行われた。通称、アイヒマン実験―本書は世界を震撼させたその衝撃の実験報告である。心理学史上に輝く名著、新訳決定版。
目次
服従のジレンマ
検討方法
予想される行動
被害者との近接性
権威に直面した個人
さらなる変種やコントロール
役割の入れ替え
集団効果
なぜ服従するのかの分析
服従のプロセス―分析を実験に適用する
緊張と非服従
別の理論―攻撃性がカギなのだろうか?
手法上の問題
エピローグ
著者等紹介
ミルグラム,スタンレー[ミルグラム,スタンレー][Milgram,Stanley]
1933年、ニューヨーク生まれ。社会心理学者。ハーバード大学で社会心理学博士号を取得の後、エール大学、ハーバード大学、ニューヨーク私立大学大学院で教鞭を執る。服従実験の業績でアメリカ科学振興協会より社会心理学賞を受賞。実験成果をまとめた『服従の心理』は世界的な反響を呼んだ。84年没
山形浩生[ヤマガタヒロオ]
1964年、東京生まれ。東京大学大学院工学系研究科都市工学科およびマサチューセッツ工科大学大学院修士課程修了。大手シンクタンクに勤務の一方、幅広い分野で執筆、翻訳を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
119
「人間がどのようにして社会的影響に服従し権威に従うか」についてヒト試験を行い、その結果と考察についての内容。「個人と社会の相互作用」、「権威は社会的構造から生まれる」、「権威への服従は人間の性質の一部」、「服従は社会的な構造や文化的背景によって強化される」、「盲目的服従(=エージェント状態)は平凡から極悪非道を生み出す」等々の考察が出るわ出るわでとても刺激的でした。面白かったからまた読もうと思いました。2026/02/13
rico
91
読みながらずっと考えてた。気軽に参加した心理学実験である人に電撃を与えることを命じられ。その人が苦痛を訴えやめてと懇願した時、私ならどうしたかと。大半が拒絶するという予想に反し、命令通りに電撃を加え続けた者多数という結果。でも当然かも。組織の命に従っただけ。その言葉の下、多くの愚行が繰り返され血が流されたことを、私たちは知っている。種、または個としての生存戦略。行為の結果に対する免責へのお墨付き。理由はあれこれ説明できても、人がそういう存在であることに向き合うしかない。これ以上過ちを繰り返さないために。2023/12/20
『よ♪』
51
ミルグラム実験──俗称アイヒマン実験。生まれつきのサイコパスなんていない。権威者から命令されると残虐な行為を容易く実行してしまうという。この状態を"エージェント状態"と呼ぶ。責任を権威者に転嫁し、結果『服従』する。実験では大多数がこれに当てはまる結果だった。時に人は、命令に従わない『非服従』という選択もする。しかし、これは私たちが期待するような道徳心からではない。見るに堪えないというストレスからの逃避が理由であり、つまりは"自分の為"だ。生まれつきのサイコパスなんていなかった。──が、結局は残念な結果だ。2022/03/19
里愛乍
48
社会心理学者の服従実験記録であり、当初はかなりの反響があったという。個人では躊躇あるいは拒否する意識を持っていたとしても、権威からの命令には従ってしまうという結果は、驚きもあるがわからなくもない。個人の責任が伴うかどうかそこで人の心理は左右される。『人殺しの心理学』を思い出した。実験による分析記録は興味深く、もう少し時間をかけて読みたいところ。さらに補遺にある批判者の意見に対する記載も面白い。世間的倫理とは一体、と考えたくなる。2020/02/03
藤月はな(灯れ松明の火)
45
社会心理学の授業でミルグラムの服従実験や監獄実験の様子を映像で見たことがある。アイヒマンの例を挙げても人間は権力によって左右された状況によって自分の行動を決めることが多い。人は他者の痛みや苦しみを自分のものとし、想像できる。だからこそ、自分が嫌がることを他者にもできない。しかし、もし、「あの人は悪い人だからどんな残虐なことをしてもいい」、「あの人のせいだから仕方ない」という題目を自ら、与えるなら?その時に人は、他者を身近に感じて想像するということを停止して従ってしまうことが多い。故に人の善意はとても、弱い2015/01/21
-

- 和書
- 広島・宮島 ことりっぷ