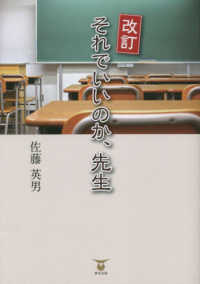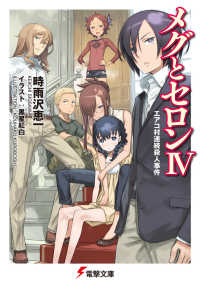内容説明
万物の死の予感から逃れ、生の中に遍在する死を逃れて錯乱と狂気のうちに太陽で眼を焼くにいたる青年ベッソン(プロヴァンス語で双子の意)の13日間の物語。ひりひりする緊張感を孕みつつ、叙事詩的な世界を生み出してきたル・クレジオは、2008年、ノーベル文学賞を受賞。その彼のデビュー作『調書』以前に書き始められた長編の、待望の文庫化。
著者等紹介
クレジオ,J.M.G.ル[クレジオ,J.M.G.ル][Cl´ezio,J.M.G.Le]
1940年、イギリス人を父に、フランス人を母に南仏ニースに生まれる。1963年『調書』でルノード賞受賞。1965年に短編集『発熱』を発表、1966年に長編『大洪水』を発表して作家としての地位を確立した。著書多数。2008年、ノーベル文学賞を受賞
望月芳郎[モチズキヨシロウ]
1925年‐2003年。東京生まれ。東京大学文学部仏文学科卒業。中央大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
35
これまで啓示めいた衝撃を幾度となく受けてきたが、本書は格別なものがあった。 ある意味、詩や詩文、詩想に疎い自分が、ル・クレジオの書を味読するのに、二十歳前に初めて『物質的恍惚』や『愛する大地』などを読んで以来、40年ほどを要したということかもしれない。 感想などは書かない。本書でも、痺れる箇所は随所にあったのだが、本書を各当時のル・クレジオの自分への違和感を抉り取ったと感じる記述を一か所だけ転記して、感想に代える。(注:以下は、本文からの抜粋です) 2019/01/01
ドン•マルロー
29
どうやら話の筋をたどるという作品ではないようだ。圧倒的な筆致、思想の奔流、言葉の大洪水を体感すればそれで良いのだろう。作品はフランソワ・ベッソンの南仏ニースでの13日間の彷徨をえがく。解説にも触れられているが、彼のさまようニースの街は、どこか神性と荘厳さとをたたえ、ジョイスの”ダブリン”と重なるところがある。それは登場人物たち、彼らの言動、様々な描写、あらゆるセンテンスが、一様にニースの街と一体となり、その総和として奇跡的な結晶を生みだしているからだろう。難解だが、得体の知れぬ力に満ちあふれた傑作だ。2016/03/04
ネムル
22
漠然と広大な海文学のイメージだったル・クレジオだが、ガラス越しに見る雨と地中に流れる暗渠のイメージをもった本作は、どこか不穏と倦怠に満ちた水文学だった。またガラス/砕けるガラスというイメージも頻出するが、スクリーンというシネマ的な雰囲気とモノへの視線の向け方は、ヌーヴォーロマンに挑発的ですらある(ただ個人的なツボではルクレジオのコップより、ロブグリのトマトのが冒険的で崇高に感じるが)。シネマ的といえば眼を焼く/フィルムが燃えるという連想もあるが、なんとなくギリシャ悲劇よりはプラトンの洞窟のがしっくりくる。2018/10/09
SAT(M)
12
主人公ベッソンが街を、あてもなく、見るもの見るもの悲観しながら徘徊するさまを、シュルレアリスム的表現を用いながら、十三日間に渡って綴った作品。ストーリー性は薄く、まさに修辞の「大洪水」は長編の詩のようです(前後の章を入れ替えても成り立ちそう…)。本道というものはなく、寄り道に寄り道を重ねているような物語の進み方で、「この寄り道の先に面白いことがありそう」と思うやいなや、別の寄り道に入り出す感じが、もどかしかったです。まさか読み終わるのにほぼひと夏使うとは…。2019/08/23
ksh
10
大洪水の名に違わず、プロローグから詩的大音響が横溢する。紙面を埋め尽くす言葉の洪水。描写のなかで色彩が煌めき、美しくも取り留めのない叙情的筆致に目が踊るのがわかる。語られる内容ではなく、その詩的な言葉の姿自体に喜びを感じる。ベッソンの十二日間の彷徨。街に佇む生の翳り、死の芳香を嗅ぎ取りながらも当て所も無く。盲目の男との出会いに、嵐の日の波間に、教会の裡に、空高く旋回する鳥の姿に彼は天啓を打たれたのだろうか。やがてベッソンはその眼を太陽で焼き尽す。視ることをやめた彼は一体、何を視ようとしたのか。2016/11/20