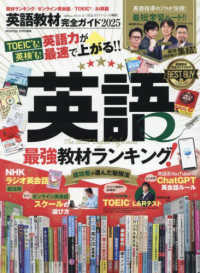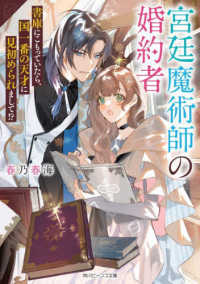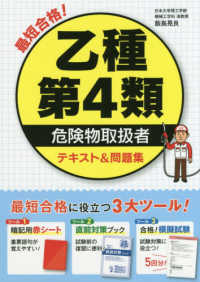内容説明
「閑さや岩にしみ入〓の声」「秋深き隣は何をする人ぞ」―俳句を和歌と同等の価値にまで高め「蕉風」を確立した俳諧の巨匠・松尾芭蕉。東北・北陸の各地を旅し、研ぎ澄まされた感性で綴られた夢幻的紀行「おくのほそ道」の新訳をはじめ、数々の名句から精選し、その文学的・詩的魅力を深く読み解く。人間存在の本質を突く十七文字の小宇宙に、現代の日本語で迫る最良の入門書。
目次
百句(波の花と雪もや水にかえり花;雲を根に富士は杉なりの茂かな;夏の月ごゆより出て赤坂や;秋来にけり耳をたづねて枕の風;行雲や犬の欠尿むらしぐれ ほか)
連句(「狂句こがらしの」の巻(冬の日)
「鳶の羽も」の巻(猿蓑))
著者等紹介
松浦寿輝[マツウラヒサキ]
1954年東京生まれ。詩人・小説家。東京大学名誉教授。2000年「花腐し」で芥川賞受賞。著書に『半島』(読売文学賞)、『川の光』、『エッフェル塔試論』(吉田秀和賞)、『折口信夫論』(三島由紀夫賞)、『明治の表象空間』(毎日芸術賞特別賞)、『afterward』(鮎川信夫賞)、『名誉と恍惚』(谷崎潤一郎賞・Bunkamuraドゥマゴ文学賞)、『人外』(野間文芸賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しずかな午後
13
松浦寿輝による松尾芭蕉「おくのほそ道」の現代語訳と、芭蕉の発句と連句についての評釈。自分は松浦寿輝の文章の楽しみは、その饒舌な文体にあると思っているので「おくのほそ道」の現代語訳はマジメな訳と思う反面、さほど面白みを感じなかった。それよりも、後半の百句の評釈にこそ真価が発揮されている。一句一句に対して微視的な精読を重ねたり、あるいはモネやボードレール等へ連想を飛躍させたり、自由自在に読みは広がる。評中には「生命力」という語が頻出するが、まさに芭蕉の句に新鮮な生命を取り戻そうとするような楽しさがあった。2024/11/29
Moish
3
日本文学全集ですでに読んでいて再読なので、ここでは今回特に気に入った句を。「五月雨や桶の輪切るゝ夜の声」。傾向として、静寂の中の一瞬の激しい変化、みたいな句や歌が好きらしい。2024/11/14
uchiyama
2
必要ではあるのだけれど、初学者には読むのが面倒な膨大な典拠を列記する解説や、まして、それでは数多ある素人俳句と芭蕉の何が違うのかわからなくなる、ありきたりな「感興」に共感するだけの感想や、が跋扈しがちな俳句周りの本の中で、そんな「文化」の楔から俳句を解き放ち、多言語には翻訳不可能な技巧を丁寧に「読む」ことで、逆に世界文学としての俳句と、芭蕉の天才を余すところなく伝えてくれる本でした。特に百句評釈は、今、俳句を組み立てていくかのようで。ところどころ反発すら感じさせる物言いも含め、折に触れ読み返したいです。2025/01/18
文化
1
俳句の十七字という制限は表現手段として厳しすぎると思うのだが、おくのほそ道では紀行文に俳句を織り込むことで言葉の世界に奥行きと一貫性を生み出している。この形式は割と革新的だったのではないか。しかし個人的には極限まで情報を削ぎ落とした俳句のミニマルな部分に美を感じるため、後半の百句の方が楽しめる部分は多かった。最も良かった俳句。「此道や 行人なしに 秋の暮」2025/07/04
Go Extreme
1
百句: 波の花と雪もや水にかえり花 雲を根に富士は杉なりの茂かな 夏の月ごゆより出て赤坂や 秋来にけり耳をたづねて枕の風 行雲や犬の欠尿むらしぐれ 皿鉢もほのかに闇の宵涼み 風色やしどろに植ゑし庭の秋 この道や行人なしに秋の暮 この秋は何で年寄る雲に鳥 月澄むや狐こはがる児の供 秋深き隣は何をする人ぞ 旅に病んで夢は枯野をかけ廻る なに喰て小家は秋の柳陰 白芥子や時雨の花の咲きつらん わが宿は四角な影を窓の月 物言えば唇寒し秋の風 連句: 「狂句こがらしの」の巻(冬の日) 「鳶の羽も」の巻(猿蓑)2024/10/04