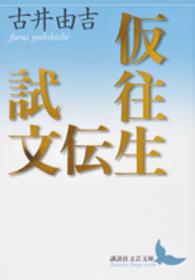内容説明
古来、来訪神は、海の彼方から、山奥から、見知らぬ世界から、つまり異世界・異次元から、鬼の姿で現れ、福音をもたらした。また、神武征服以前の土俗神たちも、異形の鬼として荒ぶる神となるが、転じて守護神となる。あずまえびす、怨霊、夜叉、鬼道、鬼門、様々な鬼に関する伝説などを考察しながら、鬼は神と捉える日本人の信仰心の原像に迫る。
目次
第1章 鬼のクーデター―あずまえびす、ヤマトに叛逆す
第2章 怨霊は鬼か―鬼となる怨霊、ならぬ怨霊
第3章 鬼を祀る神社―温羅伝説と国家統一
第4章 女が鬼になる時―舞い踊る夜叉
第5章 ヒミコの鬼道―神の道と鬼の道
第6章 鬼門という信仰―都人の祟り好き
第7章 異世界のまつろわぬ民―山人・海人・平地人
第8章 鬼の栖―縄文神への追憶
著者等紹介
戸矢学[トヤマナブ]
1953年、埼玉県生まれ。國學院大学文学部神道学科卒。専門は、神道・陰陽道・地理風水・古代史研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





ヒロの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
寝落ち6段
17
日本人は、鬼と共に生きてきた。鬼を祀る神社は多く、鬼祭は日本各地にある。諺や御伽噺に頻出し、生活習慣にも鬼は現れる。鬼は、恐ろしい者であり、力強い庇護者であった。各地に残る神になった鬼を手引きに、神の正体を紐解くと、神話時代に各地を治めていた王なのではないかと推測された。新興勢力に追いやられた王とその郎党は、深山幽谷に入り、鬼となっていったという。外国人、山賊、怨霊、被差別部落など、鬼の正体については諸説があるが、私は「鬼」の広義性が強く、正体は様々あると思っている。これもまた一つの鬼の形なのだと思えた。2025/05/21
ちび太
8
子どものころ鬼が怖かった。人間の大人が仮面を被っていると知りながら怖かった。恐怖心がどこから来たのか知りたくて読んだ。鬼は元々、神と同義。ヤマト政権が各地を征服する過程で、その土地にいた権力者(縄文人)を鬼として祀ったという説を著者は主張している。確かに納得感があるが、私の持つ恐怖心の正体は不明なままであった。2025/04/29
さとちゃん
8
2019年に単行本、2024年に文庫化。ずばり「鬼とはなにか」を論じた本書。特に面白く読んだのは第4章「女が鬼になるとき 舞い踊る夜叉」と第6章「鬼門という信仰 都人の祟り好き」でした。本書では呉市の「やぶ」を鬼の一形態として紹介していますが、地元の人曰く「やぶは鬼ではない」のですよ。筆者がどういう観点から「やぶ」を鬼にカテゴライズしたのか、機会あれば伺ってみたいです。2025/03/10
わ!
8
鬼の本まとめ読みの第四弾は戸矢学さんです。この方は、民俗学研究家なのですが「ヒルコ」や「ニギハヤヒ」など、興味深いタイトルの本を次々に書かれており、読んでみても下調べがしっかりしていて面白いのです。…で、この戸矢さんが描く「鬼」なのですが、かなりアプローチが異なります。もはや「鬼」=「まつろわぬ民」という前提で進んでいて、そんな前提から見えてくる日本史のようなものを浮かび上がらせています。(まぁ、ちょっと暴走かな…と思える論もありますが。)いろいろな神社の細かい由緒を、ポロッと語ってくれるのも嬉しいです。2024/06/12
fseigojp
7
関裕二は天皇鬼説だが、こちらは先住民族説2025/04/07
-
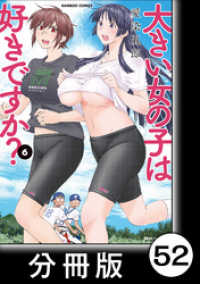
- 電子書籍
- 大きい女の子は好きですか?【分冊版】5…