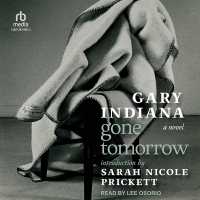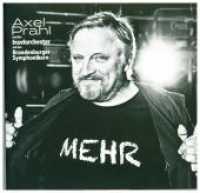出版社内容情報
精霊送りに胡瓜が使われる理由、火の玉の正体、死を告げるカラスの謎……“黒い習俗”といわれる日本人のタブーを民俗学者が解明。
内容説明
精霊送りに胡瓜が使われる理由、火の玉の正体、死を告げるカラスの謎、カエルを拝む人々の願いとは…。迷信や妖怪といった、俗信と呼ばれる分野に強い関心を持つ民俗学者が、前兆、占い、祈り、まじない、妖怪変化、迷信療法など、現代まで続く日本の不可思議な習俗の真相に迫る。
目次
第1章 未来予知法―前兆と卜占
第2章 暮しのなかのタブー―禁忌
第3章 祈りとマジナイ
第4章 霊怪現象―狐憑きと幽霊と
第5章 妖怪変化・魑魅魍魎
第6章 迷信療法―近代医学の素地
第7章 生活のなかの旧知識
第8章 日本人の運命観
最終章 迷信総論
著者等紹介
今野圓輔[コンノエンスケ]
本名・圓助。1914年8月10日、福島県相馬郡八幡村生まれ。慶應義塾大学に入学し佐藤信彦、折口信夫らの講義を受けた。在学中に柳田國男らの「民間伝承の会」に入り民俗学を学ぶ。1942年に毎日新聞社に入社、新聞記者のかたわら日本民俗学会評議員などを歴任した。1982年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
78
約57年前に出版された本だが、今読んでも刺激的な本である。茶柱が立つ理由は「考えれば、そうだ」と思いつつも可笑しい。しかし、悲観して自殺者を出すまでになった丙午生まれの俗信が教育とメディアの発達によって悪い意味で広めてしまったという指摘が遣る瀬無かった。読了後、思ったのは「時代は変わっても生活に応じて俗信も刷新して増えていく」のだという事。コロナ禍対策で提言されたいくつかもいつか、俗信の類にされる時が来るのだろうか・・・。2022/01/23
テツ
21
科学的な根拠が皆無な迷信でも、何故そう思われている(いた)のかと調べてみればそれなりの理屈はあるわけであって、現代社会に生きる人々には馴染むこともなければ理解すら及ばなくても、過去のある時代には疑い用のない社会通念として通じていたんだろう。今この令和の時代に説得力をもちぼくたちが信じている諸々だって百年後に生きる人々にとってはリアリティがなかったりするんだろうな。迷信は無知蒙昧から生まれるものではな く時代時代においてどんどんと新陳代謝を繰り返しながら変化をしていくものなのかもしれない。2021/11/13
澤水月
14
1965年初刊、翌66年丙午に向け「歴史浅く根拠ない迷信」と諄々と説く(前の明治39年に縁遠いと悲観し多数自死)。皮肉にも教育均一化により却って俗説が一般家庭に広まったためという。この件のほかはカラス、飲食などに纏わる俗信例。当時「幸福の手紙」が出回り、続けたための逮捕例、断てないのは「寝覚めの悪さ」からというのは今のコロナ禍の民間感覚に通じる核心。科学がいくら進み解明され、多くの常識人が「霊の有無」は非科学的と感じてもお盆に祖霊を敬うことや事故現場に花を手向ける心を軽んじるなという一貫姿勢に強く共感した2022/01/10
乃木ひかり
13
思っていた内容とは違ったが良書であることに違いはない。1965年に出た本であるためこの本そのものが当時の社会文化を知る助けにもなる。迷信総論最後の七行は今の日本にも大いに当てはまると思うので自称文化人・自称活動家の方々は読んでみて欲しい。本書でツブロサシに言及されていたが、今は直接的なシーンは無かったはず。どこかで省略されたのだろうか。2021/11/11
多喜夢
12
読み応えのある本だった。1965年当時に残る迷信。今も残るものとそうでないものと。カラスの鳴き声や茶柱の話題から、占い、タブー、まじない、憑きもの、幽霊、人魂、生き血・人肉食、そして鬼門や様々な暦の話など興味は尽きない。そういえば、自分も小学生時代にこっくりさんに夢中になり、幸福の手紙を書いたことを思い出した。結局、迷信・俗信はいつの時代になってもなくならない。さて近所の神社とお寺に初詣に行こう。2022/01/01