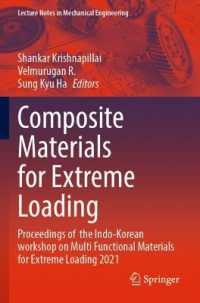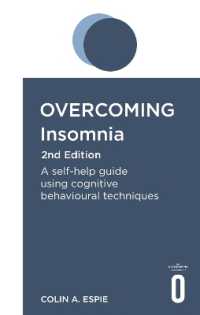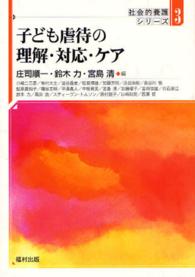出版社内容情報
「忌む」とは何か。ここに死穢と差別の根原がある。日本各地からタブーに関する言葉を集め、解説した読める民俗事典。全集未収録。
内容説明
「忌」は、外からはばかって近づかぬものと、内にあって警戒し忌でないすべてのものを排除しようとする両方に分かれ、かつ密接にからまりあっている。ここに、穢れと差別の根源がある。微々たる片いなかの事実を集積してその解明の手がかりとする“日本民俗学の前途の光”となった画期の書。不思議な習俗・風習・奇習事典。
目次
1 忌みの状態
2 忌を守る法
3 忌の終り
4 忌の害
5 土地の忌
6 物の忌
7 忌まるる行為
8 忌まるる日時
9 忌まるる方角
10 忌詞
著者等紹介
柳田国男[ヤナギタクニオ]
1875年、兵庫県生まれ。旧姓・松岡。民俗学者。短歌、新体詩、抒情詩を発表。東京帝国大学卒業後、農商務省に奉職。貴族院書記官長をへて退官、朝日新聞社に入社。1909年、日本最初の民俗誌『後狩詞記』を発表、翌10年、『遠野物語』刊。民間伝承の会を主宰した後、戦後、日本民俗学会の初代会長に。文化勲章受章。著書多数。1962年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムッネニーク
116
81冊目『禁忌習俗事典 タブーの民俗学手帳』(柳田国男 著、2021年3月、河出書房新社) 民俗学の父・柳田国男が1938年に刊行した『禁忌習俗語彙』を改題、新字新仮名としたもの。 キャッチーな書名からは想像もつかないほどに難解で、その上文体が古いのでとにかく読みづらい。 本書に収められている習俗は、今では失われてしまったものがほとんど。それを後世に伝えた柳田の功績は大きい。 〈忌を厳守する者の法則にも、外から憚って近づかぬものと、内に在って警戒して、全ての忌で無いものを排除せんとする場合とがある〉2023/09/11
里愛乍
63
事典と銘打っているだけあって、あらゆる禁忌タブーとされる民俗学手帳、忌のしきたりや意味もだけど、言葉そのものが何というか、もう強烈である。例えばツキタテ、セツバタ、ナツキト、カンバリ等こうしてカタカナで並べてみるだけでもおどろおどろしくないですか?文字としてもそうだけど音で聞くのも相当なもの。あと死を連想されるのか血がやたら忌み嫌われてる。喪が不浄なれば産も穢。世の昔から女が蔑まされてきたのは畏れからではないのか。だって毎月血を流すんですもの。2022/08/28
33 kouch
38
禁忌習俗を辞典のように羅列したもの。よくこんなに取材したな…と感嘆。葛は引き連れてくるので忌、恵比須様の竿に絡まるので食物に不自由するとか、夜山に入ると木から血が出るとか、地方色が豊富な感じで興味深く聴けた。出産や葬儀という人の生死に関わるものが多い気がする。よく箸から箸でものを取ろうとしたり、ご飯に箸を刺したりすると親から怒られた。忌事でやることを通常時にすることは禁じられている。そのためなのか、忌事はわざとぎこちなく行為が設定されているのと興味深かった。所々に入るツッコミのような柳田さんの主観がよい2025/04/28
皆様の「暮らし」を応援サポート
23
収録されているほとんどが、なぜ禁忌なのか、なぜ穢れているのかという発生源が書かれているわけでもなければ、禁を破ったらどうなるかが詳しく書かれていないものも多い。ただその些細な現象が禁となり「常」になる。それはある出来事が起こったその要因を当事者の行為や過去の状況で説明するためか、あるいはこれから起こす出来事の口実として設定されているのか、いずれにせよ、それが「常」の制度と化して人々の生活に入りこんでは衰えていく様は俯瞰できる。たとえば就活ルールなんかをありがたがる大バカ共にはこういう昔話を読ませるといい。2021/12/29
バズリクソンズ
22
柳田國男ほど日本の民俗学を真剣に研究された人物はいないのではと思う。本書カバーの後ろに忌は外から憚って近付かぬものと、内にあって警戒し忌でない全てのものを排除しようとする両方に分かれ、かつ密接に絡まりあっている。ここに穢れと差別の根源があるとの解説は本書を読む前の必要な知識ととれる。動物の呼び名ひとつとってもその地方で全く違う意味を持つ事が知れたし、忌の害や忌まれる日時は我々日本人でも遠い昔に忘れ去られてしまった風俗、風習に先祖代々受け継がれてきた重要性を改めて気付かされた。一家に一冊は持っていたい貴重本2025/10/02