出版社内容情報
戦死した画学生たちの作品を収集展示する美術館ーー「無言館」。日本中の遺族を訪ね歩き、遺作を預かる巡礼旅を描く。解説=池上彰。
窪島 誠一郎[クボシマ セイイチロウ]
著・文・その他
内容説明
戦時中に応召出征して戦死した画学生たちの作品を収集展示する美術館―「無言館」。設立に至るきっかけから、画家の野見山暁治とともに日本中の遺族を訪ね歩いて思い出話を聞きながら遺作を預かる著者の巡礼の旅。幼い頃に養父母に自分を預けた実父・水上勉との再会、一方の貧しい養父母の愛情に悔恨とともに気づく経験を重ねつつ描く鎮魂の遍歴。
著者等紹介
窪島誠一郎[クボシマセイイチロウ]
1941年、東京生まれ。作家、美術評論家、美術館館主。父親は小説家の水上勉で、幼少時に別離して養父母に預けられる。1977年に父と再会。1979年に信濃デッサン館を設立、1997年に同地に無言館を設立。翌年、『「無言館」ものがたり』で第46回産経児童出版文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- セイサイのシナリオ 25話「夫の支配」…
-
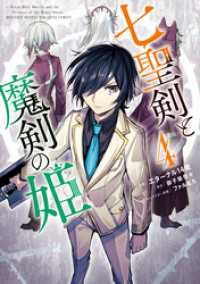
- 電子書籍
- 七聖剣と魔剣の姫(4)
-

- 電子書籍
- ゴルフレッスンコミック2017年4月号…
-
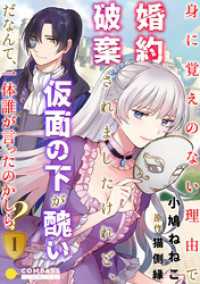
- 電子書籍
- 身に覚えのない理由で婚約破棄されました…
-

- 電子書籍
- ニューカー速報プラス 第39弾 新型 …



