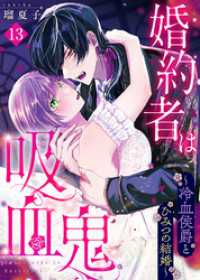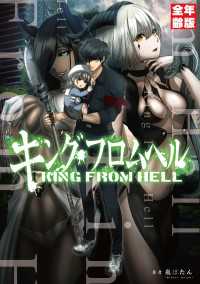出版社内容情報
近代文学の隠れたテーマ、差別・被差別問題を扱った小説アンソロジー。徳田秋声「藪こうじ」から島木健作「黎明」まで11作。
【著者紹介】
1938年岡山県生まれ。作家。河出書房新社編集部を経て著述業に。主な著書に『浅草弾左衛門』『車善七』『江戸東京を歩く 宿場』『弾左衛門の謎』『異形にされた人たち』『乞胸 江戸の辻芸人』『吉原という異界』等。
内容説明
ここには明治維新以降に書かれた作品十一篇を収録する。いずれも被差別部落に関連する内容である。問題提起、同情、に誤解がまじりもするが、弱者に目を向け寄りそいつつ、被差別者の側にも内包される差別の構造も明るみに出される。初めて文庫で編まれる被差別部落をめぐる文学史でもある。
著者等紹介
塩見鮮一郎[シオミセンイチロウ]
1938年、岡山市生まれ。河出書房新社編集部を経て、作家に(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ナミのママ😴休憩中🏥
52
明治から昭和まで、被差別部落をテーマとした11編からなる小説集です。時系列順に掲載されていますが、最初の方は旧仮名づかいに挫折しました。作品のうち、被差別部落出身者が書いたものは一作のみです。日本の文学を読むうえで、避けて通れないものだと思い、手にしました。現代の社会問題をテーマとする作品とはまた違った重いものがあります。そして、忘れてはいけない問題だと思います。2016/09/14
CTC
11
16年3月刊。当たり前だが、続編にあたる『被差別文学全集』より撰が練れている。「隠していた事を世間につきつけて、なんの責任もないのに罰を受けている理不尽さを訴えなければならない」との意図(達していると思う)。また民俗学的な意味合いも大いにある事だろう。例えば島崎藤村が記す“新平民”の特徴は、「皮膚の色が違ってる」、「皮膚病でも蔓延して」、「藁なぞ敷いて半裸体」となるが…これは全てイザベラ・バードが『日本紀行』に記している明治初期(11年)の田舎の日本人の特徴にそのまま重なるのですよね。一読の価値のある本。2017/08/10
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
8
11編中、部落出身者の筆になるのは平野小剣の「関東・武州長瀬事件始末」1編のみというのは、それだけ当事者が声をあげることが難しかったということか。2016/05/15
Kotaro Nagai
6
本書は被差別部落に関するアンソロジー。明治29年から昭和11年の短編11編を収録。徳田秋声「藪こうじ」(明治29年)と小栗風葉「寝白粉」(明治29年)、続く清水紫琴「移民学園」(明治32年)はともに雑誌「文芸倶楽部」に掲載された。どれも言文一致体ではなく文語調なので読みづらいがそれでも差別される側の苦しみは伝わる。特に「寝白粉」の6章、ヒロインの兄宗太郎の妹お桂への語りは胸打つものがある。それなのにあのエンディングはどうかと思う。鴎外、藤村や夢野久作などの作品もあるが、島木健作「黎明」が一番の力作と思う。2023/04/26
シンドバッド
4
編者がわざわざ『被差別』とする意図が理解しかねるものの、収録されている作品とその時代を今一度考えるきっかけではあった。2017/05/09