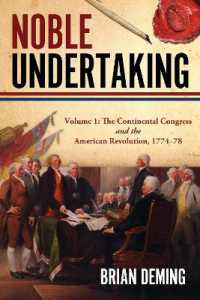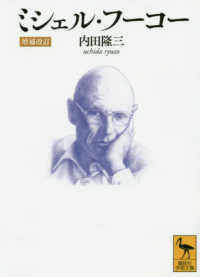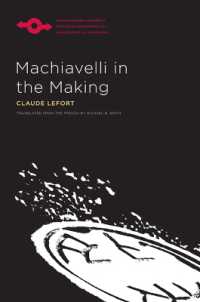内容説明
新しい情報技術が社会を変える!―私たちは何十年もそう語りつづけてきたが、本当に社会は変わったのだろうか?そもそも情報技術と社会とは、どんなかかわり方をしているのだろうか?「情報化社会」という夢の正体を、それを抱き、信じたがる社会のしくみごと解明してみせる快著。大幅増補の新世紀版。
目次
序章 「情報化」の時代―情報技術は何を変えるのか?
第1章 「情報化社会」とは何か―社会の夢・夢の技術
第2章 グーテンベルクの銀河系/フォン・ノイマンの銀河系―人間‐コンピュータ系の近代
第3章 会社は電子メディアの夢を見る―ハイパー産業社会のコミュニケーション
第4章 近代産業社会の欲望―「情報化」のインダストリー
第5章 超近代社会への扉―二一世紀の社会と情報技術
補章 情報化社会その後―一五年後の未来から
著者等紹介
佐藤俊樹[サトウトシキ]
1963年、広島県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。専攻は比較社会学・日本社会論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
84
レビュで気になり、すぐ近くの図書館にあり借りる。1996年の本を2010年の文庫化で修正、補論を加えた本。著者によると60年代後半から半世紀に渡って、情報化社会論というものが数え切れないほど現れては消えていったという。新しい技術で社会が変わるというもの。そのくせ、社会自体はそこまで変化したのだろうか?と著者。この情報化社会論というものの本質とそれを求める我々近代社会の欲望と夢を考察していく。この本以後もまた同じような話がある。ビッグデータ、AIなどがそうだ。思い出しても、マルチメディアとかあったな。良書。2018/12/02
masabi
11
新技術が社会を変えるという未来像を提示する言説がなぜ流行るのかを解説する。技術決定論に対して、社会の仕組みが技術の使われ方を決めるという立場から言説の背景を腑分けする。社会のあり方を選択することへの重責の免責にこの言説が持て囃されるという。最近では仕事の内容が激変するとまでは言われても社会が変化するというのは少なくなっていると思う。web3.0くらいか。社会の仕組みが新技術の採用や普及にも関わる。インターネットがボランティアによるコミュニティ、それがアメリカ建国期の反復だというのもおもしろい指摘だった。2025/02/11
ぷほは
6
メディア系の講義をする際にはまず技術決定論から如何に距離をとるか、という話をするのだが、みんなびっくりするくらい簡単に飲み込まれていく。「こんなにAIやスマホが進歩して、未来が楽しみになりました😊」みたいな感想が死ぬほど提出され、ぐったりしてしまう。しかし、そう書く気持ちも痛い程よく分かる。というか講義中に私だって実はそうした語り口に安易に乗っかってしまう時があるのだ。学生はそれを感知し「こういう風に書いておけば先生喜ぶだろうな」と反省しているに過ぎない。1996年の話ではない、2024年の社会の話だ。
チェリ
6
「情報技術により社会が変わる」と60年近く同じことが言い続けられているが、実際には期待されていた様な大転換は起きていない。この本の初版は1996年に刊行され、改訂版が2010年に作られたが、改訂時に殆ど内容は変わらなかったという事実が裏付けにもなっている。私が読んだのは2022年だが社会の潮流は変わっておらず、AI、DX、Society 5.0など情報技術が社会を変えるという夢は語られ続けている。何故この様なことが起きているのか?それは情報技術が人間のアナロジーとして認識されているためだと著者は指摘する。2022/01/29
前田まさき|採用プロデューサー
6
痛快!人口知能が騒がれてひさしい今こそ、読み返したい一冊。本書によれば、「情報化社会」など未だかつて到来していない。しかし我々は「情報化社会」を夢見るがゆえに、手を変え品を変え、それっぽい言説を生み出してしまう。そのたび、周辺産業は盛り上がるものの(ex.人口知能が取り沙汰されると、人工知能関連のメディアやサービスが立ち上がる)、当初騒がれていた「情報化社会」は到来しないままブームは終わる。その繰り返し。その意味で、「情報化社会」は近代産業社会と共犯関係にある。なんとも説得力があり、かつ皮肉な考察だ…。2019/05/01
-
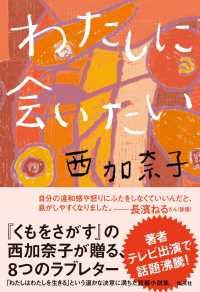
- 和書
- わたしに会いたい