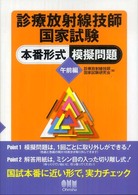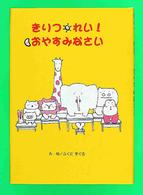内容説明
黒い瞳の伯爵夫人と呼ばれた日本人女性、クーデンホーフ光子の生涯を克明に追い、東京の町娘が伯爵家に嫁いだ事情、落日のハプスブルク家でジャポニスムの象徴となったその人となり、両次大戦の荒波に翻弄されながらも「パン・ヨーロッパの母」と称えられた数奇な生涯を豊富な写真とともに追う。
目次
湯河原にゆかりの人を訪ねて
ヴェールに包まれた光子の生い立ち
結婚の秘密
恋に落ちた伯爵
クーデンホーフ家とは
外交官の妻になる
祖国を離れて
ボヘミアの伯爵夫人
子供たちとの距離
ある日突然、未亡人に
ウィーンでの新しい生活
ハプスブルク帝国の崩壊
病気、孤独、そして望郷
運命にもてあそばれる子供たち
著者等紹介
シュミット村木眞寿美[シュミットムラキマスミ]
1942年東京都生まれ。早稲田大学大学院修了後、ストックホルム大学に留学。69年よりミュンヘンに在住して執筆活動を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
James Hayashi
31
「天蓋の船」玉岡かおるを読んで興味を持っていたクーデンホーフ光子(青山みつ1870ー1941)激動の時代である。渡った国オーストリアで死に別れ、残った子供7人と第一次世界大戦を迎える。パン・ヨーロッパの母とも呼ばれ、苦労されたこともわかる。しかし歴史的な逸材とはいえない。著者が細かく調査されているがある、ミツコ自身歴史的な役割がなされていない為、読み足りなさがある。リヒャルト・クーデンホーフ=カレルギーは彼女の次男であるが、いい親子関係を持っていないので書けないのであろう。2019/03/05
Midori Nozawa
10
よく調べて書き上げた本。ミツコという明治初年に生まれた女性の人生を興味深く読むことができました。オーストリア代理公使として東京に来たハインリッヒ35歳に一目で見染められた。まだ17、8歳の娘ミツコ。二人の男児を続けて出産し、未知の国での生活が始まる。相手は侯爵。お城に住む。7人の子どもを産むが、34歳で突然未亡人に。男4人女3人の母は日本に一度も帰らなかった。第一次大戦、日清戦争、日露戦争、第二次大戦の時、ドイツ、チェコ、オーストリア等の戦いが描かれ、次男リヒアルトはEUのもとを作った人と知った。2020/07/24
Mie Shida
5
明治にオーストリアへ嫁いだクーデンホーフ・光子の話はまったく知らなかったのでボヘミア、国籍が四回も変わったという当時のヨーロッパの情勢も合わせて興味深く読んだが、実は何度か読みかけて挫折してしまっていた本。シュミット村木さんの丹念な取材は面白いが、読み物としては少々辛かった。同じ文章を何度か読んでも文意を汲み取れないものが多々あったのは彼女もドイツ在住の女性だったからなのか。メキシコのポランコ地区で有名なマサリク大統領通りがチェコの初大統領の名だというのも知らなかったので面白い発見だった。2012/06/17
ロピケ
5
本当は、『クーデンホーフ・光子の手記』を先に読んでいたんだけれど、なかなか読み進めず、ついこの本に手を出したら、良い調子で読めてしまった。あの時期に外国人と結婚、たとえ相手が由緒正しい貴族で尊敬に値する人柄であっても、光子の家族にとっては、体面、世間体ということもあって、複雑な経過を経ているため、歯切れの悪い個所も間々あった。光子と子どもたちの確執。息苦しくなる。読みながら、『ウィトゲンシュタイン家の人びと』、『わたしは英国王に給仕した』、『マサリクとの対話』の内容が思い起こされた。2011/08/04
noémi
4
以前、松本清張の「暗い血の旋舞」っていうのを読んだけど、やっぱり、日本にいてヨーロッパというかハプスブルグ帝国のような多民族国家に住む人の気持ちを理解するのには無理があるんだなぁとつくづく感じた。2010/10/16