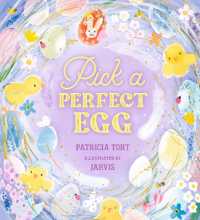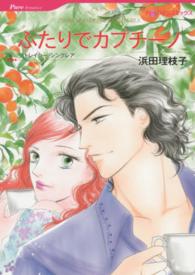内容説明
その起源は戦国時代にまでさかのぼる「舌耕芸」落語の歴史を、詳細な調査と、落語家たちへの限りない共感をもって描き出した本格的落語通史の前編。この「江戸・明治篇」では、落語の原点「咄」の誕生から、御伽衆の活躍、寄席の成立、三遊亭圓朝の登場、明治の上方落語の盛衰までを描く。詳細な資料研究と落語家たちの生きた声の取材をもとにして綴る、画期的な落語通史の前編。
目次
序章 落語名義考(咄と噺と話;咄から落語へ)
1章 近世前期の咄―御伽衆から職業的咄家の時代へ(落語の原点;仕方咄の成立;辻咄と座敷咄のはじまり;浮世草子と落し咄)
2章 近世後期の咄―寄席咄の全盛時代(上方の会咄;江戸の会咄;寄席咄時代のはじまり;江戸戯作と落語)
3章 明治の東京落語―名人円朝の登場(三題咄の流行;三遊派の形成;柳派その他の動静;落語会のアプレ・ゲール;東京落語の再出発;明治の大衆文学)
4章 明治の上方落語―分裂から凋落へ(桂派の台頭と分裂;桂派と浪花三友派の競合;落日をまねく“反対派”)
著者等紹介
暉峻康隆[テルオカヤスタカ]
1908‐2001年、鹿児島生まれ。文学博士。近世文学を専攻し、なかでも西鶴をはじめとする江戸戯作文学の研究を行い、早稲田大学などで教鞭をとった(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kiiseegen
0
戦国から江戸、明治迄の落語通史。極端に江戸落語に片寄らず、しっかりと上方落語も描き込まれて良い。上方種の大量移植は何故に行われたかが知りたかったが良く理解出来た・・・。あと鸚鵡籠中記に米沢彦八の急死が記されているのには驚いた~。2014/02/06
あだこ
0
軽妙に語りつつ、かつハメは外さない。江戸が重厚で、系譜的に繋がっているし、新しさもある。しかし明治はこんなにあっさりしていていいのだろうか。大正・昭和篇に期待。2009/10/24
いちはじめ
0
著者は近世文学専門の国文学者なだけに、江戸時代の文献史料に目が行き届いているのが強みか。落語の歴史を知る上で貴重な本2008/01/04
-

- 和書
- フォークナーと日本文学