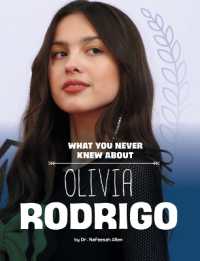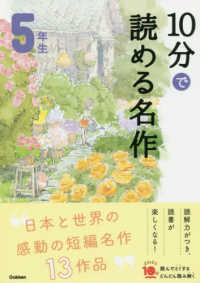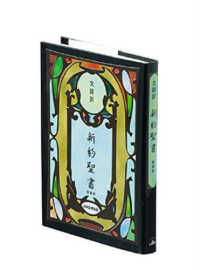内容説明
日本橋は浮世小路といえば『百川』だ。「なに、袈裟がけに四、五人斬られた?」話をまくらに、落語ゆかりの東京各地を訪ね、落語の話に絡めながらその土地の今昔を綴る道中が始まる。全五十四話、一話に一点の挿絵も自筆、稀代の落語通にして名随筆家の著者がのこした、落語ファン必携のイラストエッセイ集。
目次
うきよ珈琲こちらでござい―日本橋浮世小路
ぬほんばすの最期―日本橋
従五位上近江守源兵衛藤原鼻利―日本橋・通り一丁目
心学の尾〓(てい)骨―長谷川町三光新道
あらもったいなや―馬喰町
佃の佃煮―佃島
お忍び視察は日本の伝統?―数寄屋橋
赤井御門守はご名君―丸の内
民のクレーンにぎわいにけり―千代田
七ツ屋の終焉―麹町1〔ほか〕
著者等紹介
江國滋[エクニシゲル]
1934年、東京都生まれ。エッセイスト。慶應大学法学部卒業後、新潮社入社、『週刊新潮』編集者を経て文筆業に。落語を始めとする大衆芸能に関するエッセイや紀行文、スケッチの分野でも活躍。俳号“滋酔郎”を名のる俳人でもある。1997年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
33
古典落語の舞台となったゆかりある東京の各地を、ペン画のイラストを添えてのエッセイ。とはいえ、元となった同書の初刊行は1970年(復刊文庫化に伴い大阪京都はオミット)ゆえ、すでにその景色もほぼ失われており、アーカイブを開いたらさらに古いファイルが見つかった様なノスタルジーを味わうにはかなりの年配者となるのでは。次、次々世代が読むことを予め目論んでの、「風土記」というタイトルであればさすがであるが、落語自体リアルタイマーでなくても、その世界の中で愉しめるのであれば。2023/09/30
ふーてー
3
図書館本。本との出会いは一期一会だから、と思ってなんとなく惹かれるままに借りてみた。読んでいて、まだこんな風景が東京にあるんだろうか、と行ってみたくなった。落語の江戸〜明治と地続きの、「すっかり変わってしまった」と書いているけど、21世紀の現在よりは、まだずっと懐かしい。落語に描かれた風景が少しは記憶にある人が語ると、今もちゃんと当時とつながって見える。場所の記憶というのは、こういう落語や随筆につなぎ留められて、積み重なっていくんだな。江國滋さんによる挿絵も、旅(散歩?)情緒をかきたててくれる。2016/06/15
feodor
2
江國さんの落語本、なかなかのもの。俳句本も読みたいのだけれどもなあ。 落語の舞台となった都内の名所を訪れて、スケッチがてらのエッセイ、というもの。 江國さんが訪れた時期が昭和45年。いまから40年以上も前の話で、その頃残っていた下町情緒なども今はなくなっているのだろうな、という気もするけれども、そんな情緒をイラストも交えて紹介するこのエッセイ、読んでいてほっとする感じがある。2010/01/25
hitsuji023
1
落語についてのエッセイ。落語好きなら、楽しめるのではないかと思います。2019/10/29