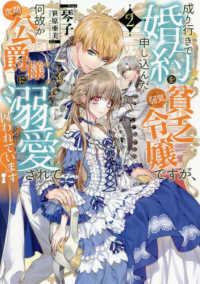内容説明
江戸の人は芝居をシバヤと読み、ついこの間までシバイと読むとお国はどちらと訊かれたものだ。江戸に限らず、都会人は言葉の使い分けを心得ていて、落語の熊さん八さんも、鼠小僧も、いざとなれば今日の紳士以上に礼儀正しい言葉を使ったものだ。江戸東京の言葉の移り変り。黙阿弥の思い出。明治の寄席と芝居。半八捕物帳の誕生譚…。情趣あふれる綺堂の名随筆選。
目次
江戸のことば(戯曲と江戸の言葉;孝子貞女 ほか)
怪談奇譚(夢のお七;鯉 ほか)
明治の寄席と芝居(寄席と芝居と;明治以後の黙阿弥翁 ほか)
創作の思い出(自作初演の思い出;「半七捕物帳」の思い出 ほか)
著者等紹介
岡本綺堂[オカモトキドウ]
本名敬二。1872年、旧御家人を父として東京に生まれる。東京府中学校卒業後、東京日日新聞に入社。記者の傍ら戯曲を書き、『修禅寺物語』『番長皿屋敷』等の名作を発表。定評ある江戸風俗の確かな知識は、人気を博した捕物帳の嚆矢『半七捕物帳』シリーズ、『三浦老人昔話』等の小説に遺憾なくいかされている。1939年死去
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
チャーリブ
45
「綺堂随筆」2冊目。「ことば」に関する随筆は最初の3つぐらいで、あとは、寄席や芝居に関するものが多いですね。14歳の綺堂が円朝の牡丹燈籠を聴きに行ったときの話など読むとこの天才的噺家の芸の凄みがよく伝わってきます。時代が天才を作るという綺堂の分析は的確です。しかし「ことば」については、当時の一部の人たちが「している」を「してる」、「して仕舞う」を「しちゃう」と口にするのを下等だと不愉快に感じているところなど、いつの時代にも共通する老人の憤慨のようです。「怪談奇譚」のような老人の昔話はいいですね。2023/06/07
hitsuji023
8
いつも通りの心地良い語り。特に落語好きの私としては、岡本綺堂が円朝の牡丹灯籠を直に聞いて、その話術に感心したエピソードなどに羨ましさを感じた。その綺堂はこうも書いている。もし円朝が現存していたならば、寄席はどうなるか。円朝が寄席を征服するか、それとも時勢に対抗できず漫談や漫才におされるか。綺堂は後者だろうと言っている。「円朝は円朝の出ずべき時に出たのであって、円朝の出ずべからざる時に円朝は出ない」私は今の時代の芸を見逃さないようにしたいと思う。2023/11/26
東森久利斗
7
これぞ随筆。個人の見聞、体験、意見、感想などを, 特定の形式にとらわれずに,筆のおもむくまま自由に書き記す。規格商品的な大衆文化としてエッセイというジャンルが生まれる前、無法地帯的な荒地であった時代の奇蹟。御一新後の消え行く文化や慣習、言葉へのとりとめのない思いを江戸っ子らしい飾らない文体で綴る。池波正太郎のエッセイにも通づる郷愁感と焦燥感。2019/01/03
rouningyou
5
円朝の高座をランプの灯りの下で聴いて、帰りの夜道を逃げるように帰ったとか、いかにも街灯もない時代であろうから怪談、しかも名人の怪談は心底怖かったろうと思う。円朝が新作を作るにあたって取材の旅を日記にしており、大変な苦労をして一作を作り上げているという。また、黙阿弥に関して「筋立てが余り巧妙でない」ときっぱり言い切っていて、黙阿弥の複雑に絡み合った話が余り理解できないのは自分の実力のせいと思っていたがそればかりでもないことを知った。2014/06/08
しちこ
5
言葉というものに並々ならぬこだわりを持っていたのだなあと感心せられた。読んでいて古くて読みづらいと感じることは全くないが、円朝の落語を生で聞いたり、黙阿弥翁に会ったりという記述が出てくると、ああその時代の人なんだと我にかえって思う2012/05/28