内容説明
1970年代中期にあって、三大思想家の代表作を、驚くべき力わざで読み解いた、先駆的であると同時に、いまだに比肩する書のない歴史的な名著。
目次
1 肖像画家の黒い欲望―ミシェル・フーコー『言葉と物』を読む
2 「怪物」の主題による変奏―ジル・ドゥルーズ『差異と反復』を読む
3 叙事詩の夢と欲望―ジャック・デリダ『グラマトロジーについて』を読む
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シッダ@涅槃
37
◆理系研究者の我が畏友が言ったヘーゲルを愛読しているという言葉に影響され、俺もなにか“反時代的”な書物を愛読したいと思ってたなか、嬉しくも早速見つけてしまった感がある。その理由は本書を貫く物事からの“すり抜け”、あるいは“逃走”(本書には出てこないがドゥルーズの用語)への強い希求にあると思う。◆「事件=できごと」のあまりの凶暴さに、白痴化し、ぴらんとした1枚の白い薄膜状になった自分の上に電気的に生起する再「事件=できごと」、そんなものを思う。決して「破壊と創造」ではなく、本書のいう「不実なる反復」。2018/08/30
シッダ@涅槃
22
大変面白かったが、第3章デリダ論中頃から「とりあえずの終章」にかけて、突然読むのが辛くなり、遅々として進まなくなった。難解なのもあるが、前回読んだとき「ミステリのような手際」と評したのはなぜ?と首をかしげたくなる。前回はほんとちんぷんかんぷんだった第1章フーコー論は、未だに「顔と瞳の相互離脱」がなにを指しているか分からないながら、次第に身についてきたような気がする。第2章ドゥルーズ論は掛け値なしに面白いが、蓮實先生にしては通りがよすぎるかもしれない……。愛読、再読を待ってるかのような書物。2022/12/31
しゅん
13
再読。でもあまり理路は追えず。おそらく、三人(というより『言葉と物』『差異と反復』『グラマトロジ―について』の三冊)に対する蓮實の記述の共通点は、「書き方の変化自体に力が宿る」という点の強調だろう。変化を消してしまえば力も消えるのだから要約しても意味がないのであって、変化を「反復」するために、それぞれの「作品」との出会いを演出するのが作者の仕事となる。デリダに対してはやや批判的なスタンスというか、その「真面目さ」と距離を置いているように思えた。1978年当時にこの三人ってどんな立ち位置だったんだろう。2022/09/20
Nobody1
2
解説本ではない。2014/10/06
立川がじら
1
今はもう書店では手に入らない本で、図書館所蔵のものを読みました。 フーコーの『言葉と物』、ドゥルーズの『差異と反復』、デリダの『グラマトロジーについて』。これらについて語りながら、それらについて語ってはいないのかもしれないということでどこまでも開かれていきます。それらがそのような本になった(製本された)ことの秘密をなぞるように、この『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』も綴じられており、(私が読んだこの一冊は)図書館の中で次の読者を待ち受けているのだなと思います。2021/01/15
-
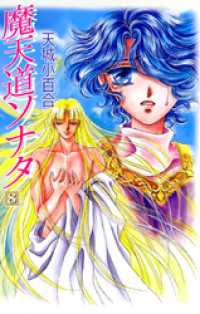
- 電子書籍
- 魔天道ソナタ 8巻 まんがフリーク
-
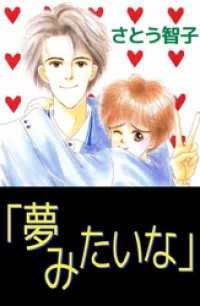
- 電子書籍
- 「夢みたいな」 1巻 まんがフリーク
-
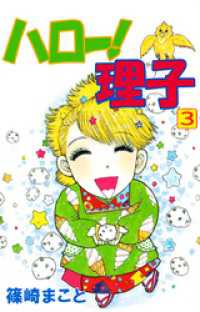
- 電子書籍
- ハロー!理子 3巻 まんがフリーク
-
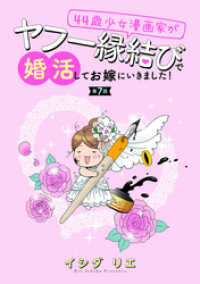
- 電子書籍
- 44歳少女漫画家がヤフー縁結びで婚活し…
-
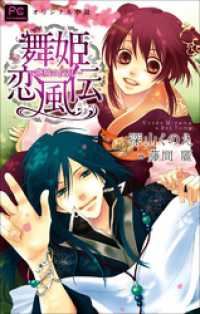
- 電子書籍
- FCルルルnovels 新装版 舞姫恋…




