- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
大和ことば、みやびな日本語、失いたくない日本語…を七十二候に当てはめながら精選。日本人が大切に受け継いできた言葉を愛でる本!
内容説明
情緒あふれる郷愁のことばをじっくり味わう。「暦」や「歌」に散りばめられた、季節のかすかなうつろいを表す語句とは。
目次
春(立春 りっしゅん…2月4日頃;雨水 うすい…2月19日頃 ほか)
夏(立夏 りっか…5月5日頃;小満 しょうまん…5月21日頃 ほか)
秋(立秋 りっしゅう…8月7日頃;処暑 しょしょ…8月23日頃 ほか)
冬(立冬 りっとう…11月7日頃;小雪 しょうせつ…11月22日頃 ほか)
著者等紹介
齋藤孝[サイトウタカシ]
1960年、静岡県生まれ。東京大学法学部卒。同大大学院教育学研究科博士課程などを経て、明治大学文学部教授。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。NHK Eテレ「にほんごであそぼ」総合指導。著書に『声に出して読みたい日本語』(草思社・毎日出版文化賞特別賞受賞)、『身体感覚を取り戻す』(NHK出版・新潮学芸賞受賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
b☆h
43
四季を七十二候で分け、その時期に関する言葉を解説つきで各4つずつ紹介している。以前、夕立を〝狐の嫁入り〟と言って、職場の年配の方に驚かれたことを思い出した。私ぐらいの年齢がギリギリ知ってる言葉なんだろうか…こうして、知らない世代が親となり、言葉は使われなくなっていくんだな、と寂しくなった。だからこそ、時々昔の言葉を知る機会を作っていかないと、と改めて思わされた。季節も言葉も、やっぱり初夏が好きだな。立夏に薫風、若葉萌える、漁火、せせらぎ、宵待草がお気に入り。由来や語源を知れたのも良かった。2022/09/19
オシャレ泥棒
2
図書館 △2022/01/16
Go Extreme
2
春:立春 雨水 啓蟄 春分 清明 穀雨 夏:立夏 小満 芒種 夏至 小暑 大暑 秋:立秋 処暑 白露 春分 寒露 霜降 冬:立冬 小雪 大雪 冬至 大寒2021/05/18
-
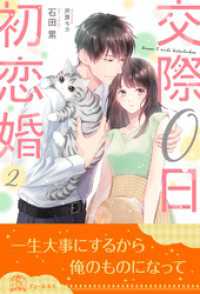
- 電子書籍
- 交際0日初恋婚【2】 チュールキス






