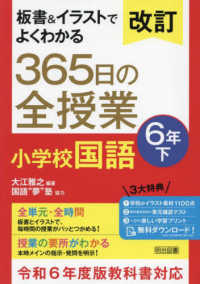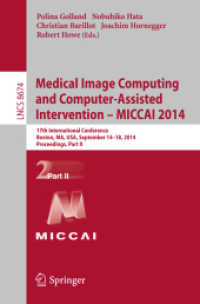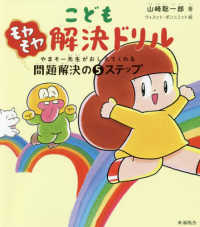出版社内容情報
時間とは何か? 生命とは? 宇宙の果ては……科学の最先端に手を伸ばす人々の想像を様々に喚起し、日常に新しい見方を与える38のエッセイ。ゆっくり歩いても、かなり遠くまで行けます。
池内 了 (イケウチ サトル)
1944年生、京都大学大学院理学研究科物理学専攻修了。理学博士。国立天文台教授、名古屋大学教授等を経て総合研究大学院大学教授、現在は同大学理事。主書に『疑似科学入門』『科学の限界』『物理学と神』他。
内容説明
ゆっくりでもよし。引き返してもよし。宇宙、素粒子、医療、生命…その最先端をめぐりながら、自然の不思議に出会いなおす、38の扉。
目次
第1章 日々の科学―科学は誰のもの?(時間の多様性について;心を切り換える秘策 ほか)
第2章 科学の共有知(科学のことば;共同幻想としての「疑似科学」 ほか)
第3章 科学者の顔(科学者の二つの顔;高学歴ワーキングプア ほか)
第4章 「科学趣味」(書くことへの熱中と楽しさ;産業・科学映画は時代を映し出す鏡 ほか)
第5章 “最先端”が照らし出すもの(ノーベル賞と基礎科学の将来;科学のコミュニティ ほか)
著者等紹介
池内了[イケウチサトル]
1944年兵庫県生まれ、1972年京都大学大学院理学研究科物理学専攻修了、理学博士。国立天文台教授、名古屋大学教授などを経て、2006年より総合研究大学院大学教授、現在は同大学理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
18
池内教授は、2つの課題をもって、行き詰まり回避を しているという。 行きつ戻りつ、ということだ。 私なら、読書会運営と中山間マネジメント論の 良好な関係を築ければよい。 その合間に、アルバイトではあるが。 池内先生は、農業を、「地力を利用して 有用な植物を栽培耕作する有機的生産業」 としている(34頁)。 専門用語は一つの言葉が使用される地域 によって音韻・語彙・文法的な相違が 生じるという意味で方言に似ている(59頁)。 共同幻想は埴谷雄高が提唱(68頁)。 2014/04/21
kiho
7
科学と世の中を結び付けて語ってくれている☆エッセイ風でもあり、科学研究のスポットの当たらない部分についてもわかりやすい説明が…折しもスタップ細胞の話題が注目を集めているが、研究環境の現状についてのコメントもあり、興味深かった♪2014/04/13
バチスカーフ
5
宇宙物理学者による科学についてのエッセイ。視点のブレが少なく、「科学」に対しての信頼と懸念のバランスが良い。一方で、どうしても入門的な印象も否めなかった。中学~大学生あたりにはぜひ読んでもらいたいと思った。2014/03/09
お抹茶
2
科学と社会を中心に綴ったエッセイ集。一つの問題で行き詰ったときは,意識して無関係な問題を考え出し,それに熱中すると気分は爽快になる。装置が大型化した今では10人以上の連名論文も増え,部分知の寄せ集めになり,全体を見渡せる科学者が不足する。さまざまな専門を持つ学芸員をプールし,そこから博物館や美術館に派遣するという方法を提唱する。産業革命後は科学・技術の力を権力が利用せざるを得なくなった。ニュートンは神秘学最後の巨人であり近代科学の創始者。2018/12/05
乱読家 護る会支持!
2
宇宙物理学、生物学から政治まで、科学的思考によるエッセイ。やはり、クラブ的思考をされるので、それぞれのテーマを深堀されて、本質をつかもうとされる姿はステキ、、、でも、ハート型で直観型の今のわたしには、なんだか物足りない。なんか、ぶっ飛んだ結論がないと、なーんだか読んだ気がしないのでツル。2013/10/26
-
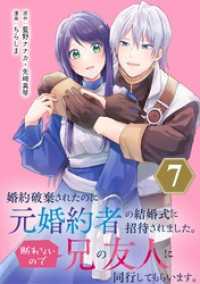
- 電子書籍
- 婚約破棄されたのに元婚約者の結婚式に招…