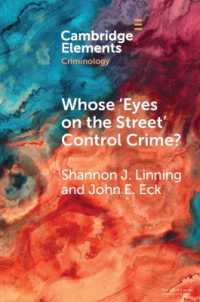内容説明
無意識と心の病の関係とは?日常生活における不安や苦悩の意味を理解する…。私たちはなぜ、「本当の自分」を知りたいのか?自分の心の中には自分でもわからない部分がある…。自由意志は存在しないのか?科学や哲学は無意識に何を見出したのか…。そもそも、無意識とは何なのか?人間という存在の本質を解明する“無意識の現象学”へ…。
目次
序章 無意識を問う
1章 無意識の発見―深層心理学の歴史から考える
2章 無意識はあるのか?―科学の研究と哲学の視点
3章 無意識とは何か?―現象学から本質を考える
4章 無意識はいかにして生まれるか?―心の発達にともなう身体化
5章 不安の生み出す無意識の行為―精神病理から考える
6章 無意識を活かす方法―自己分析と心のケア
終章 自由であるための無意識
著者等紹介
山竹伸二[ヤマタケシンジ]
1965年、広島県生まれ。学術系出版社の編集者を経て、現在、心理学・哲学の分野で批評活動を展開している。評論家。同志社大学赤ちゃん学研究センター嘱託研究員。桜美林大学非常勤講師。現代社会における心の病と、心理的治療の原理、および看護や保育、介護などのケアの原理について、現象学的な視点から捉え直す作業を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kentake
2
私たちの日常の多くは無意識の行為に支えられている。全ての行為を常に考えて意識して生活していたのでは、必要以上に心配や焦燥が発生し、平穏な日々を送ることができなくなるという。しかし一方で、考えずに行動することは、うまくいっているうちは良いが、問題が生じた場合には原因や理由が見えてこないという欠点もある。 このような不可解な無意識の世界について、心理学や心理療法という観点における様々な考え方を交えて解説されており、考えさせられる。著者によれば、無意識の本質は、自己了解にあるという。2024/10/04
Go Extreme
2
フロイト・無意識の発見者 欲望の力と抑圧の力のせめぎ合い→無意識の現象 ユング・分析心理学・個を超えた集合的無意識の構造 精神分析諸学派ークラインとラカン ロマン主義→無意識への関心 自由に必要な自己理解→本当の自分→無意識への関心 フッサールー意識の不可疑性 無意識≒自分を知ること・自己了解 不安の発生→不安回避行動→適切・歪んだ反応→自己ルール・歪んだ自己ルール 不安に対する不安→不安の増大/パニック 習慣化しだ行動・感情・イメージ→無意識の自覚=自己了解→無意識の自己ルール・自己像・自己理解の修正2024/05/22
ちもころ
1
全く理解できず。2024/07/01