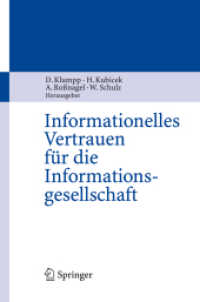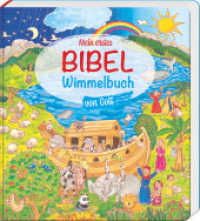内容説明
お岩はなぜ殺されたのか?怪談の現場を歩く。本邦怪談の最高峰、鶴屋南北「四谷怪談」。その下敷きになった実話を元に、ゆかりの江戸の土地土地を探る。その場所の意味とともに、背景の忠臣蔵の陰画ともなった、伊右衛門ほか苦しい浪士たちの実態を追う。
目次
序章 わたしの四谷怪談
第1章 浅草観世音境内
第2章 宅悦住居と浅草裏田圃
第3章 雑司ヶ谷と隠亡堀
第4章 深川三角屋敷
第5章 夢と蛇山庵室
著者等紹介
塩見鮮一郎[シオミセンイチロウ]
1938年、岡山県生まれ。作家。河出書房新社編集部を経て著述業に(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
7
著者は穢多や乞胸などの被差別民をテーマにした小説とともにこの分野での考証等幅広い活動で私には馴染みの深い文筆家である。本著は長編小説「車善七」と並行してWeb上に発表した文章を書籍化した物という。地誌とはあるがその性格は薄いし洩れがあり妥当でない所がある。専ら新潮古典集成本と岩波文庫版を参照しつつ芝居を突き合わせて書き上げている。私も芝居を見ており隠亡堀の戸板返しや蛇山庵室等馴染んでいる。この演目は忠臣蔵のアナロジーへの拘りから本書指摘通り筋立てに矛盾が多い。その点圓朝の怪談のほうがよく練られていると思う2020/10/11
マカロニ マカロン
7
個人の感想です:B。歌舞伎やお芝居で知られる『東海道四谷怪談』はなぜ「東海道四谷」なのだろうかと以前から思っていた。新宿区左門町の「於岩稲荷」の案内文にはこの地に伊右衛門もお岩も実在したらしい。しかし、芝居の舞台は豊島区雑司ヶ谷の四家町。鶴屋南北が芝居を書くにあたって、時の権力の取り締まりを避けるため、忠臣蔵の時代を室町時代に替えたようにカモフラージュで「東海道の四谷」と書き換えたようだ。実際に両方の場所を歩いてきたがどちらも今では住宅密集地帯で怪談話は無縁の土地。お寺は多いので、古い場所なのは確か。2019/05/20
マカロニ マカロン
5
個人の感想です:B。『東海道四谷怪談』という歌舞伎や芝居で人気の出し物がある。なぜ「四ツ谷」が東海道なんだろう?と前から疑問だったが、忠臣蔵で時代を室町時代に書き換え、江戸を鎌倉に置き換えたように取締りへの対抗策として架空の場所として「東海道の四谷」をカモフラージュにした。鶴屋南北が四谷怪談を書く100年前の戯作「四谷のお岩」等、いくつかの話を組み合わせて作った。新宿区左門町に伊右衛門もお岩も住んでいた。怪談の舞台は豊島区雑司ヶ谷の「四家町」に移されている。今はどちらも住宅密集地で怪談話の面影もない。2019/05/20
fritzng4
2
四谷怪談の「四谷」が新宿の四谷ではなく現在の雑司が谷(旧四家町)なのだと知ったのはつい最近のこと。それが結構新鮮な驚きで江戸時代の地誌に興味が湧いて手にとったのだが、地誌というより丁寧に原本を紐解いての解題という感じで求めていた内容とは些か違っていた。とはいえ四谷怪談の物語世界への理解度は深まったのだが原典の問題か最後の方が急激につまらなくなる。2025/08/21
やま
2
夏の課題のため再読2014/06/23