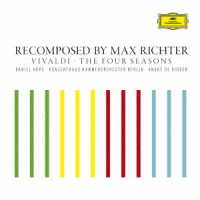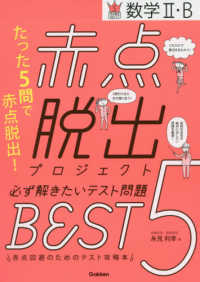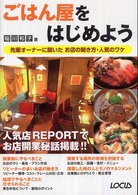- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
歴史の教訓がよみがえる。被災を乗り越え、新しい文章を付して、名著復刊。
目次
1 「津波常習海岸」の「宿命」(急がれている津波研究;津波の言い伝えと発生)
2 明治二十九年の大津波(一八九六年六月十五日)(“狂瀾怒涛一潟千里の勢い”;「日清戦争」祝勝気分のなかで ほか)
3昭和八年の大津波(一九三三年三月三日)(恐慌と不況、戦争への道行きのなかで;小説『綾里村快挙録』の里 ほか)
4 チリ波津(一九六〇年五月二四日)と津波防災(チリ津波とその特徴;防災と故・田中館愛橘博士の名言)
著者等紹介
山下文男[ヤマシタフミオ]
1924年、岩手県旧綾里村(現三陸町)生まれ。地震、津波、災害に関するノンフィクション作家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。