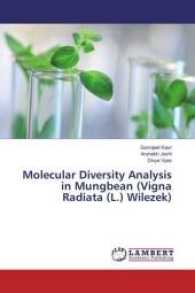感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
らぱん
42
①純粋さが時に痛々しいが面白かった。60年代の学園紛争に00年代の神社合祀政策が絡み、政治と時代が文学的に語られる。惹き込む力があり読むには易しいのだが、簡潔な説明が難しい。学園紛争の渦中にあった男が30歳を越え総括を試みる。かつての同志Nに宛てる手紙とその中に60年代当時の様子が戯曲として差し挟まれる形式で、物語内の現在80年代と情景の70年代、回想の60年代、探索の00年代、時代を重層的に捉え核にあるものを探る。まつろわぬ民の物語は、断絶が生じさせた空虚がいまここにあることを言っているように思う。↓2019/10/31
マリリン
24
198・から遡って回想するかのようなNへの通信。時代は1960年代後半から...、若者の血が熱く燃えた全共闘。即興の時が奏でられていた箱の中の親指ほどの小さなもの... 戦いの残影のような描写が美しい。散り散りになった闘志の一人Nを追い、半島の奥の林の中で見つけた小さな祠の存在やNの奇妙な行動、《死者》橘素子・《語れない石》N・《叫ぶ鳥男》の僕。最後に書かれている散文詩。橘素子の手で書かれた文字...風のクロニクル。失われた魂の蘇生と、白い小さなものの鎮魂を想う。 2020/01/30
まんだよつお
9
1906年の神社合祀反対運動、1969年の早稲田大学第二学生会館占拠闘争。先の闘争に斃れた男女は輪廻転生し、時空間を異にした次の闘争でも《死者》《語れない石》となって残酷な運命を繰り返す。通信、戯曲、情景描写と、さまざまな手法で重層的に描かれるまつろわぬ者たちの《年代記》。この手法は同じ作者の『パルチザン伝説』でも使われているが、さかのぼれば『されどわれらが日々』にたどり着く。ここで僕は本書のヒロイン橘素子と、『されど』のヒロイン節子の相似形に気がつく。困難な状況下、常に前に進もうとする孤高の女性として。2022/02/24
...
4
学生運動とはなんだったのか、史実を知りたければまぁ色々手はあるし、wikiでも良いんだけど、当時の空気や、雰囲気を知りたければ物語の力に頼るのが良いのではないかと思う。今でいえば全員中二病!これだけ月日が立っても、逆にいえば、精神的にはなんにも変わってない。良い小説。2012/04/24
うさやま
1
60年代から70年代の革命の時代を生きた学生達の辿った生死を、4人の劇中劇と司祭の末裔である友人Nへの手紙という形を取りながら描こうとした作品。少し驚いたのは、神社の神官であり続けることが20世紀初頭以降においては天皇への反逆という意味合いを持っていたということ。なぜ作者は国家神道とそれまでとを峻別するようなアプローチを取りながら天皇制の暴力性を描こうとしたのか、とても興味を持った。2023/02/19