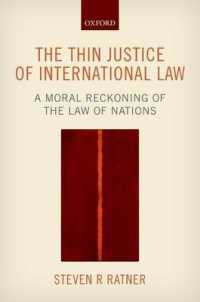出版社内容情報
マニュアルでは解決しない、緩和ケアの悩みに答えます!
「麻薬ってどう使い分けるの?」「腹水は本当に抜いて大丈夫?」「薬のせいでせん妄になったと言われたら?」「鎮静をどう説明する?」「患者から早く死なせてほしいと言われたら?」――。本書は“3学期”構成となっており、さながら1年間の講義を受けているような流れになっています。23ある講義はすべて生徒の疑問から始まっていて、新城先生がその問いに一つひとつ丁寧に答えます。マニュアルだけでは解決しない、緩和ケアの悩みに答える一冊です。
【著者紹介】
しんじょう医院院長
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねころじ
7
先生、わたしはもう限界なんでしょうか。そんな患者さんの言葉に、何も言えなかった。何て言えばよかったのか、そんな気持ちでこの本を手に取った。この本を通して、医療者も患者の死に傷つくことを知った。ホスピス、在宅ケアの経験から、現場で困った時の対処についてアドバイスが載っている。処方例とかは中堅医師向け。いつまでも悩み傷つく仕事だが、やりがいを感じる。2016/02/10
A
7
本書は緩和ケアの臨床現場の実態を一緩和ケア医の視点から解説したもの。死に至るプロセスや苦痛の緩和方法、医療者と患者と家族との間に必要なコミュニケーション方法などが、医療従事者ではない自分にも分かりやすく解説されており、緩和医療のイメージを掴むのに役立った。約三割の患者が死ぬ前に苦しむらしいけど、でもその時には(持続的な深い)鎮静で意識レベルを下げてくれるらしいので、苦痛に関してはそこまで心配しなくていいのかと少し安心した。積極的安楽死を法制化しなくても、苦痛は鎮静でなんとかなるという認識でいいのかな?2015/06/24
OHモリ
6
●刺激的なタイトルだけど内容はまっとうな良書だ。前半症状緩和のText的内容、しかしこの本のキモは後半の2学期3学期と初頭のオリエンテーションだ。 ○「インフォームドコンセントという名の呪い」●については全く我が意を得たりだった! ●緩和ケア医がナイーブな自己と現段階で思うところをさらけ出した著作。生々しくて面白いだけではなくてすごく役に立つはず。誰の役に立つの?緩和ケアに携わる医療者の役に立つということは緩和ケアを受ける側の患者さんの役にも立つはずだと思う(付箋多し)・・鎮静ガイドライン読み返しせねば2018/07/09
こんころ
1
部分読みしかしていなかったので、本日通しで読みました。著者の思慮深さには毎回はっとさせられます。「患者の病気を医療者が取り上げてはいけない」、これだけの経験と思考を重ねてきた方の言葉なだけに重みがあります。2016/09/19
totoroemon
1
表題からはもっときつい内容かと思われたが緩和医療を必要とする多くの人に読んでほしい。2015/08/22