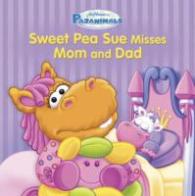内容説明
日仏の都市計画制度に見る地球環境への取り組み―“都市の上に都市をつくる”都市再生、生物多様性を明記する都市計画法、都市の成長を規制するゾーニングなど…クルマ社会やスプロールから徹底的に決別。ホンモノの持続可能な都市計画制度。
目次
第1章 「クルマを減らす」と宣言した国
第2章 都市再生が自然を守る盾
第3章 都市計画で二酸化炭素を減らす
第4章 ゾーニングによる都市の成長管理
第5章 市町村レベルで取り組む地球規模のエコ
第6章 美しい景観が引き出す持続可能性
著者等紹介
和田幸信[ワダユキノブ]
1952年、栃木県足利市生まれ。76年、東京工業大学建築学科卒業、83年同校博士課程修了。91~92年にかけてパリ第八大学フランス都市計画研究所にて住宅の改良と再利用を研究する。2003年、「フランスにおける歴史的環境と景観の保全に関する一連の研究」により日本建築学会賞(論文)を受賞。2011年、『美観都市パリ―18の景観を読み解く』(鹿島出版会、2010)で不動産協会賞を受賞。専門は都市景観、とくにフランスの景観整備に関する制度と実際の運用(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ろべると
10
著者が住む足利市と同規模のフランスの地方都市であるディジョンは、バスの利用者がニ桁も多いそうだ。フランスでは都市計画において住居地区と農業などの非居住地区を区別し、居住地に交通やインフラなどを集中させており、電線の地中化なども可能となる。建築は文化であり都市景観の重要性が共通認識として培われているので、規制に対する反対も少ないのだろう。さらには排水に含まれる二酸化炭素まで考慮するほどの環境への意識。一方の日本と言えば、無秩序に商業・工業地域にまで家が建ち、インフラが整った中心部は空洞化している。この違い!2023/03/25
ozapin
0
フランスのディジョンの都市計画の部分を読んでいて、都市計画の目的のひとつに交通費の抑制があがっていることが興味深かった。その理由としては、公共交通を使っている人の多い人があげられるようで、著者はご自身が住む栃木ではディジョンの100分の1も公共交通が使われていないと嘆く。が、思うに、こういう背景があってこそ、日本の軽自動車などは技術発展が進んだのだろうなとも思った。2015/01/04
フルカラフル
0
ヨーロッパでは、環境問題に対するために、「規制」という形をとることが多いように思う。その一例としての、都市計画についての本。 まちづくりの失敗は機会の喪失であり、そして何より荒廃・破壊への一歩となってしまう。都市計画を地球環境を結び付ける人は少ないが、それではいけない。個人によらない大きなスキームをいかにコントロールできるかが、深刻な社会問題に対処するためにこれから必要なことだろう。2018/10/26
-

- 電子書籍
- 私を探さないで10 NETCOMICS