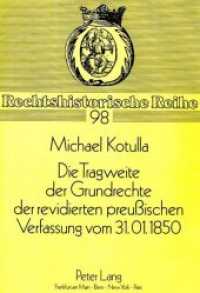出版社内容情報
歌舞伎からオペラまで、古今東西の名作で読み解く劇場デザイン原論。祭礼と伝統芸能、花道と桟敷席、オーケストラピットと舞台構成、距離感と場所性。五感に響く演劇と音楽の空間の根源性をホール設計の第一人者が説く。
内容説明
歌舞伎からオペラまで、古今東西の名作で読み解く劇場デザイン原論。祭礼と伝統芸能、花道と桟敷席、オーケストラピットと舞台構成、距離感と場所性。五感に響く演劇と音楽の空間の根源性を劇場計画の第一人者が説く。
目次
第1章 生成する劇場空間
第2章 祭りから歌舞伎小屋へ
第3章 リアルからメタフィジカルへ
第4章 オペラ劇場におけるオーケストラピットの存在感
第5章 活動と呼応する距離感
第6章 日本の劇場創成期
第7章 劇場のモダンデザイン
著者等紹介
本杉省三[モトスギショウゾウ]
日本大学教授、劇場建築計画・設計。1950年神奈川県生まれ。日本大学大学院理工学研究科修士課程修了。日本大学理工学部助手、文化庁文化部嘱託・非常勤職員(第二国立劇場設立準備調査担当)、ベルリン自由大学演劇研究所留学、ベルリン・ドイツオペラおよびシャウビューネ劇場特別研究員、DAAD(ドイツ学術交流会)奨学生などを経て、1999年より現職。おもな劇場計画担当に、シアターコクーン、新国立劇場、まつもと市民芸術館など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
6
現代の劇場は多メディア化した空間として、ビルディング建築による多目的ホールが多くを占めている。著者はこの現状を祭礼や伝統芸能の痕跡が残る歌舞伎小屋から辿りながら、演劇と建築の関係を材質や形態だけでなく、自然照明の薄暗い中で想像力を働かせる多焦点的な演劇が人工照明のフラットなスペクタクルへ変わる近代以後の西洋化に、その転換点を見出す。中近世への劇場空間への回帰を主張する本書には、劇場空間の近代化を図ったバウハウスの中で、音、光、運動、形、空間におけるイメージ空間として劇場を捉えたモホリ=ナギの主張が重なる。2025/08/25
Hiro
4
劇場建築のこれからをにらんで源流をさぐる本。こういう話を学生時代に聞き出せなかった事になんて時間と環境を無駄にしてたのかと…自省。とはいえ勉強不足でわからないことだらけ。もうすこし勉強してまた読みます。2016/09/28