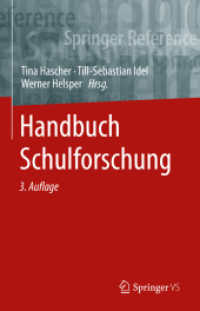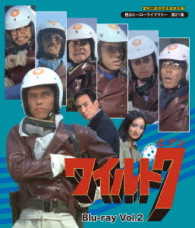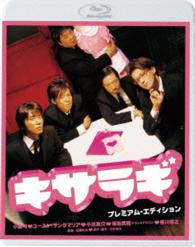内容説明
街に生き生きとしたふれあいを育てる屋外空間の条件とは。人々の日常の活動に焦点を当て、都市のスケールから街角のディテールまで、きめ細かく論じる。
目次
第1部 建物のあいだのアクティビティ(屋外活動の三つの型;建物のあいだのアクティビティ ほか)
第2部 計画の前提条件(プロセスとプロジェクト;感覚、コミュニケーション、規模 ほか)
第3部 集中か分散か―都市計画と敷地計画(集中か分散か;統合か隔離か ほか)
第4部 歩く空間・時を過ごす場所・細部の計画(歩く空間―時を過ごす場所;歩く ほか)
著者等紹介
ゲール,ヤン[ゲール,ヤン][Gehl,Jan]
1936年生まれ。1960年デンマーク王立芸術大学建築学部卒業。米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ヨーロッパ各国で研究・教育・実践に携わり、王立芸術大学建築学部教授を経て、現在、ゲール・アーキテクツ主宰。1993年すぐれた都市計画業績に対して贈られる国際建築家連合のパトリック・アバークロンビー賞を受賞
北原理雄[キタハラトシオ]
1947年生まれ。東京大学工学部都市工学科卒業。同大学院修了。名古屋大学助手、三重大学助教授を経て、千葉大学大学院教授。工学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
都市機能を重視したモダニズム建築は建築物と人間を計測可能な単位(モデュロール)とし、道を輸送路として扱った。一方その批判を展開する本書は、人間を活動する者として扱い、街路を人々が活動する場とし、建築物は公共空間と繋がる心地よい居場所の一つに変えた。公共空間の設計者である著者は本書で、活動を他者の存在を前提とする社会活動、個々人の気分による任意活動、目的をもって起こる必要活動に分ける。こうして歩くという人間の基本活動を中心に、人々が出会い、語り合い、出来事を生み出す場として都市が構想される(1971刊)。2025/07/06
摂津の鰻。
2
課題の参考になりました。2019/11/25
Naoyuki
1
屋外空間を設計する上でのさまざまな大切な知見が散りばめられていた。 屋外空間は他人との出会いの場として機能し、花壇の水やりや、買い物などの何かの口実で、人は屋外で過ごす時間を作り出しているということ。屋外空間は目的地になるのではなく、何かの目的の途中に偶然出会う要素が強いということ。人は屋外の境界に滞在したいと感じるなど。 日本では必ずしも難しいかもしれないけれども、屋外空間を、どう他人との出会いの場として創れるか、考えてみたいと思う。 2024/06/01
しゅう
1
自動車社会から脱却し、歩行者中心のまちづくりが志向されている昨今。ヤン・ゲールが自身の観察から紐解いた空間と活動との分かちがたい関係は、空間デザインに携わるものとして強く意識しなければならないと感じる。 屋外活動の3つの型として、必要活動、任意活動、社会活動(合成活動)を挙げているが、特に物的条件により改善可能な任意活動をどう増やすかがデザインの肝になる。活動が織り合わされてできるコミュニティにも注意を払い、活動やコミュニティが生まれる物的条件(特にエッジのデザイン)を提言している点が、非常に示唆に富む。2023/03/21
Tatsuo Mizouchi
0
☆☆☆ 初版は1971年だそうです。70年代には現在問題とされている課題は一通りでていたんだよね。日本の場合は高度経済成長とバブルがあり、見過ごされてきた。バブル崩壊後は新しいことを始める体力がなくなった。そして、為政者はいまだにここで問題とされているアプローチをとり続けている。2018/01/02
-
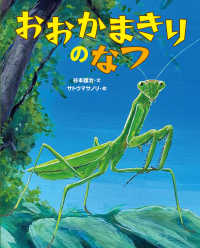
- 和書
- おおかまきりのなつ