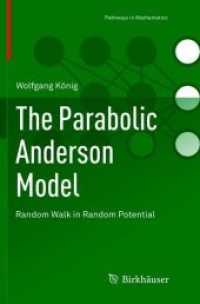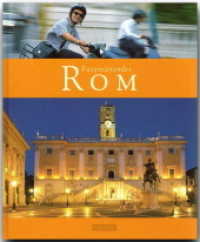感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nbhd
18
だらだらと建築の本を読んでいて、辿り着きたい到達点がぼんやり見えてきていて、それが空間。建物の見た目でも内装でも充実の機能的設備でもなく「空間の感覚」。篠原さんの言葉は、こういう関心に直撃した。「すまいというのは広ければ広いほどよい」とか「人間と空間とのやりとりということのなかにだけしかリアリティをもちえないような、本当の無駄な空間」っていう言葉。からだが空間をかんじて、脳ミソや言葉を経由せず、批評の言葉が見当たらないような、そういう感覚に辿り着きたいと考えていて、この「考えていて」も消えていくような…2017/09/15
パダワン
8
社会人向け建築設計の学校で、スタジオの先生が勧めてくださった一冊。 後半、思想的な言説が抽象度が高すぎるため難解だった。建築の学校を出ていないことが私のコンプレックスなのだが、建築の学校に行くとこういう文章を難なく読めるものだろうか? 篠原一男さんの建築は写真でしか見たことがないが、とても象徴的な空間だ。空間を作っている、とハッキリ言える。私は技術は身につけて来たが、空間を作ることに至ってない。それには思想と知識が足りないのだと思う。日々頑張るしかない。2022/05/19
roughfractus02
7
60年代日本でのモダニズム建築批判からメタボリズム建築への動向以後の方向性を指したという本書には、現在から見ると欧米のポストモダンの建築論と呼応するかのような都市へのランダム性やカオスの導入という主張がある。一方、その基点となるのは、都市でも巨大建築でもない。人が住む住宅こそが建築家が産業社会から情報社会にシフトする対峙可能なベースであると著者は捉える。本書によって、建築概念は長い間芸術の領域下にあった美的な作品から創作的な建造物にシフトする一方、建築が都市から後退する契機となったという評価も出てくる。2025/08/02
Usako
3
無駄な空間こそがその住宅のコアになる。。理性では都会の機能的な駅近アパートが便利とわかっていながら、自分の家としては何かが違うというもやもやを言語化してくれたなぁと。 住宅は芸術である、なぜなら人間の様々な感情の動きと深く関わることによってのみその存在が保証される。工業発達に伴いその対決軸として文化創造に参加するもの。。 わびさびは、生産を離れた貴族たちの無常感、虚無感。。権力の上で立ち向かえない大名へのレジリエンスとして発展した茶室建築。。文化の成り立ちを考える上でも参考になる論を展開。2021/03/29
masshi
3
住宅は芸術である。nLDKに代表される機能重視の住宅が次々と建てられていく中で、空間の無駄や不自由さこそが豊かな暮らしの原点となっていくことを論じた篠原一男の論文集。日本の伝統を設計の「原点」としながら、都市の文脈と切り離された新たな住宅の形を提案していく。欠如した空間が周辺へと働きかけ、その集合体が都市の外形を形作っていく。コロナ禍の現代にこそ住宅のあるべき姿を見直す必要があるのでは無いかと考えさせられる1冊だった。2021/02/10
-
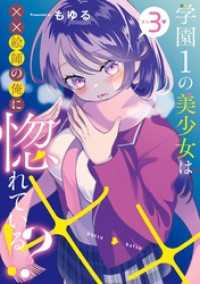
- 電子書籍
- 学園1の美少女は××絵師の俺に惚れてい…