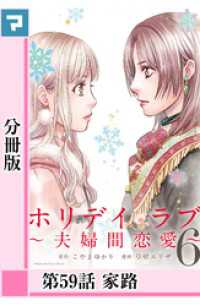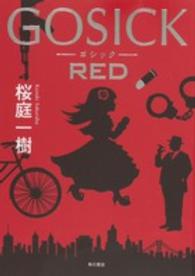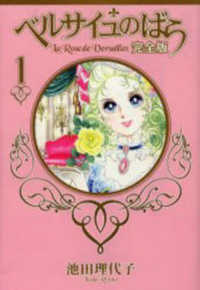出版社内容情報
江戸時代を通して書き継がれた笑話集「噺本」の謎に、新たな視点で迫る!
再録や改作を繰り返す性質から
作り手や創意に不明な点が多い噺本。
噺本を文字化された文芸として捉え
会話に付される記号「庵点(いおりてん・?)」の使用方法など
従来見過ごされてきた表記・表現の面から検討。
新たな手法で噺本を読み直し作り手の実像、その創意に迫りながら
近世文芸史上のさまざまな謎の解明に挑む。
はじめに
凡例
第一部 「はなし」の定義
第一章 噺本研究史
はじめに/一、前期噺本/二、後期噺本/おわりに
第二章 「噺」と「咄」 ─噺本にみる用字意識─
はじめに/一、「話」の用字/二、「咄」の用字/三、「噺」の用字/四、「咄」と「噺」の併用/五、作り手の用字意識/六、「噺本」と「咄本」/おわりに
第二部 噺本にみる表記と表現
第一章 噺本における会話体表記の変遷
はじめに/一、上方軽口本と江戸小咄本/二、庵点に関する先行研究/三、庵点の出現/四、明和・安永期以後の軽口本/五、洒落本にみる会話体表記/おわりに
第二章 噺本に表出する作り手の編集意識 ─戯作者と噺本─
はじめに/一、朋誠堂喜三二/二、山東京伝/三、感和亭鬼武/四、十返舎一九/五、曲亭馬琴/六、烏亭焉馬/七、その他の個人笑話集/おわりに
第三部 謎につつまれた噺本の作り手 ─山手馬鹿人を中心に─
第一章 大田南畝・山手馬鹿人同一人説の再検討
はじめに/一、『蝶夫婦』書誌/二、『蝶夫婦』の構成/三、『蝶夫婦』と庵点の用法/四、南畝の噺本三部作と『蝶夫婦』/五、『蝶夫婦』と『話句翁』/六、山手馬鹿人と洒落本/おわりに
第二章 山手馬鹿人の方言描写
はじめに/一、馬鹿人の洒落本と方言/二、洒落本における田舎言葉/三、『粋町甲閨』と仙台方言/四、『蝶夫婦』初編と南畝噺本三部作における田舎者/五、他の噺本との比較/おわりに
第三章 山手馬鹿人と洒落本
はじめに/一、馬鹿人の文体/二、洒落本における少女/三、「子ども」の描き方/四、馬鹿人以前、そして以後/五、『南客先生文集』の作者/おわりに
第四部 噺本作者の横顔 ─瓢亭百成をめぐって─
第一章 瓢亭百成の文芸活動
はじめに/一、百成の閲歴/二、百成の噺本/三、咄の構成とその特色/四、『山中竅過多』/五、百成をめぐる人々/おわりに
第二章 瓢亭百成の著作 ─未翻刻資料の書誌および翻刻─
?『福山椒』(享和三年〈一八〇三〉)
?『華の山』(文化二年〈一八〇五〉)
?『百夫婦』(文化元年〈一八〇四〉)
?『舌の軽わざ/とらふくべ』(文化三年〈一八〇六〉)
?『申新版落咄 瓢孟子』(文政七年〈一八二四〉)
?『一口はなし 初夢漬』(文政十三年〈一八三〇〉)
初出一覧
あとがき
索引【人名・作品名】
藤井 史果[フジイ フミカ]
1977年、富山県立山町生まれ。2001年、青山学院大学文学部日本文学科卒業。2012年、青山学院大学大学院文学研究科日本文学・日本語専攻博士後期課程修了。博士(文学)。現在、青山学院大学非常勤講師。
内容説明
江戸時代を通して書き継がれた笑話集「噺本」の謎に、新たな視点で迫る!再録や改作を繰り返す性質から作り手や創意に不明な点が多い噺本。噺本を文字化された文芸として捉え会話に付される記号「庵点(〓(いおりてん))」の使用方法など従来見過ごされてきた表記・表現の面から検討。新たな手法で噺本を読み直し作り手の実像、その創意に迫りながら近世文芸史上のさまざまな謎の解明に挑む。
目次
第1部 「はなし」の定義(噺本研究史;「噺」と「咄」―噺本にみる用字意識)
第2部 噺本にみる表記と表現(噺本における会話体表記の変遷;噺本に表出する作り手の編集意識―戯作者と噺本)
第3部 謎につつまれた噺本の作り手―山手馬鹿人を中心に(大田南畝・山手馬鹿人同一人説の再検討;山手馬鹿人の方言描写;山手馬鹿人と洒落本)
第4部 噺本作者の横顔―瓢亭百成をめぐって(瓢亭百成の文芸活動;瓢亭百成の著作―未翻刻資料の書誌および翻刻)
著者等紹介
藤井史果[フジイフミカ]
1977年富山県生まれ。2001年青山学院大学文学部日本文学科卒業。2012年青山学院大学大学院文学研究科日本文学・日本語専攻博士後期課程修了。博士(文学)。2015年第31回太田記念美術館「浮世絵研究助成」受賞。現在、青山学院大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。