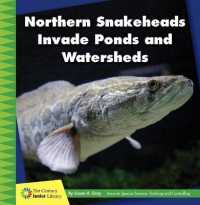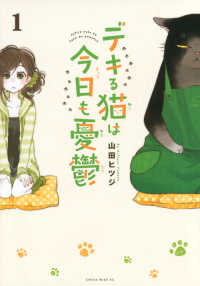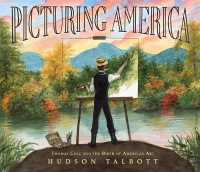内容説明
古代から現代、『日本書紀』から『妖怪ウォッチ』まで、文学・絵画・民俗資料や小説・マンガ等の中で、異類はどのように表現され、背後にどのような文化的要素があったのか。異類の文化を解き明かす初の入門書!参考文献ガイド、異類文化史年表付!
目次
総論 異類文化学への誘い
1 妖怪(総説 描かれる異類たち―妖怪画の変遷史;前近代から現代へ 変貌するヌエ;現代から前近代へ ゆるキャラとフォークロア―ゆるキャラに擬人化される民間伝承)
2 憑依(総説 憑依する霊獣たち―憑き物、神使、コックリさん;前近代から現代へ 狐憑き―近世の憑きもの・クダ狐を中心に;現代から前近代へ ペットの憑霊―犬馬の口寄せからペットリーディングまで)
3 擬人化(総説 擬人化された異類;前近代から現代へ 擬人化された鼠のいる風景―お伽草子『隠れ里』再考;現代から前近代へ 物語歌の擬人化表現―童謡とコミックソングのはざまで;西欧の擬人化事情 西欧の擬人化表現と日本漫画の影響)
著者等紹介
伊藤慎吾[イトウシンゴ]
國學院大學・非常勤講師。物語研究・室町文化史・キャラクター文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
20
「異類の会」メンバーによる論集。本格的な学術書ではなく、かなり自由度の高い作り。古代の怪異から現代のゆるきゃらに至る多種多様な題材に加え、一人の執筆者が何本も論文やコラムを寄せる独自のスタイルで、好きなものを好きなだけ書いている。編者の伊藤慎吾にしてからが、専門である中世文学に寄せた話をするかと思えば東方Projectや「およげ!たいやきくん」について熱弁を振るう有様。この闇鍋的な雑駁さが、正体定かならぬ「異類」を語るにはふさわしいのかもしれない。2025/03/15
CCC
12
妖怪を憑依・擬人化の観点で読み解く本だと勝手に思っていたのだけど、妖怪・憑依・擬人化、それぞれ別個の扱いっぽかった。だから『およげたいやきくん』やら、ゆるキャラやら、妖怪とは直接無関係な耳目を引くネタもポンポン出てくる。かく言う私も東方に釣られました。真面目な話もやるサブカル本、といった立ち位置か。2018/08/14
midorino
8
人が恐れることや理解できないことに姿を与え、恐れ敬う対象にしたり親しみを感じるようになったりというのを大まかな歴史をつかむように説明している本。妖怪といえば私は水木しげるを思い浮かべるけれど、それすら新しい方の姿だというのに気づかされる。擬人化キャラクターと妖怪の違いの説明が興味深かった。絵画における異類形態、異形形態、人間形態の描き分けについても詳しく見てみたいと思った。2016/12/14
うえ
6
巻末の年表が便利。「598年 聖徳太子、神馬黒駒に乗って富士山を飛び越える。619年 近江国で人魚が捕獲される。627年 陸奥国で狢が人に化ける。644年 赤牛、人のように立って歩く。675年 牛馬犬猿鶏の肉食を禁じる。684年 丹波国に十二本の角を持つ牛が現れる。768年 春日明神が常陸国から鹿に乗って春日野に来る。819年 京都に白龍が現れ、暴風雨に見舞われる。931年 数百匹の狐の群れが東大寺の大仏を礼拝する。1138年 神泉苑で蝦蟇たちが合戦する。1148年 法勝寺で天狗が歌を詠んだという。」2025/07/04
phmchb
6
コラムで東方projectの話が載っていたので読んだ。2017/01/05
-

- 電子書籍
- 海ガールは大海獣の夢を見たい!BLUE…