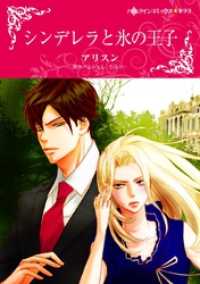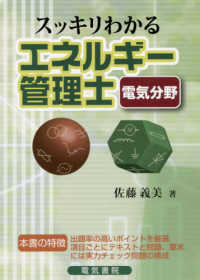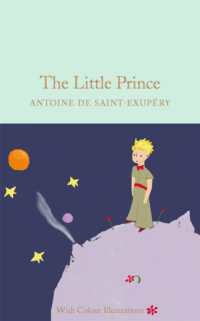内容説明
戦後文学や現代文学の礎が築かれた、1935年を軸とする前後5年間に巻き起こった「文芸復興」を検証することから、近代日本の文学史自体を相対化し、見直していく。戦後文学・現代文学の読解の新たな可能性を導き出していく書。
目次
第1部 文学史の形成と「文芸復興」―平野謙の文学史観を中心とする戦後研究の検証(戦後批評と「文芸復興」―一九五〇年代;純文学論争への道程―一九六〇年代;「神話」化された「文芸復興」―一九七〇年代以降)
第2部 「純文学」外の要素と「文芸復興」―ジャーナリズム・大衆文学を中心に(企図された「文芸復興」―志賀直哉「萬暦赤絵」にみる既成作家の復活;「円本ブーム」後のジャーナリズム戦略―『綜合ヂヤーナリズム講座』を手がかりに;読者意識と「大衆文学」―純文学飢餓論争にみる「文芸復興」の底流;黙殺される「私小説」―直木三十五「私 眞木二十八の話」にみる文学ジャンルの問題)
第3部 「モダニズム文学」の命脈と「文芸復興」―「新興芸術派」の位置(「文芸復興」期における「新興芸術派」の系譜―龍胆寺雄から太宰治へ;「文芸復興」期における文学賞の没落と黎明―「『改造』懸賞創作」と「芥川龍之介賞」;「ナンセンス」をめぐる戦略―井伏鱒二「仕事部屋」の秘匿と「山椒魚」の作家の誕生;「私」をめぐる問題―牧野信一「蚊」にみる「文芸復興」の一源泉)
第4部 「文芸復興」からみる太宰治―新進作家の登場(「通俗小説」の太宰治―黒木舜平「断崖の錯覚」の秘匿について;生成する“読者”表象―太宰治「道化の華」の小説戦略;市場の芸術家の「復讐」―「道化の華」と消費社会)
著者等紹介
平浩一[ヒラコウイチ]
1975年、兵庫県生まれ。早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。早稲田大学大学院文学研究科修士課程・博士後期課程、日本学術振興会特別研究員(DC2→PD)などを経て、国士舘大学文学部准教授。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。