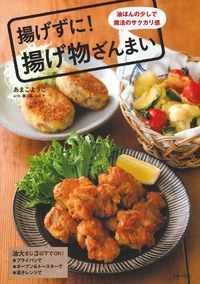内容説明
華やかな活躍をみせた宮廷歌人・額田王とさまざまに才能を開花させた歌人たちが織りなす、古代和歌の豊かな世界。
目次
篭もよ/み篭持ち
大和には/群山あれど
やすみしし/我が大王の
秋の野の/み草刈り葺き
熟田津に/船乗りせむと
香具山は/畝火を愛しと
冬こもり/春去り来れば
味酒/三輪の山
綜麻形の/林の先の
茜草指す/紫野行き/標野行き〔ほか〕
著者等紹介
梶川信行[カジカワノブユキ]
1953年東京都生まれ。日本大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。現在、日本大学文理学部教授、博士(文学)。『万葉史の論 山部赤人』(翰林書房・1997、上代文学会賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
348
「熟田津に船乗りせむと月待てば潮も適ひぬ今は漕ぎ出でな」ーあまりにも有名なこの歌との最初の出会いは中3の国語の教科書でだった。人麻呂の「東の野の…」とならんで掲載されていた。古今歌や新古今歌もあったはずなのだが、それが何だったかのは忘れてしまった。それだけ、これらの万葉歌のインパクトが強かったのだろう。もっとも、わかりやすいというのもあるのだが。この歌は、空にかかる月、海、「漕ぎ出でな」の力強い情動と、まことに雄渾な、まさに万葉歌を代表する一首だろう。当時は額田王を文字通りに王、もしくは女王と捉えていた⇒2022/11/01
しゅてふぁん
51
再読。こうして初期万葉の歌だけを読むと、家持の時代の歌との違いが良く解る。‘声の歌の世界’と考えられている初期万葉時代、その独特なことばの響きにとても惹かれる。かつて言葉には不可思議な力(=言霊)が宿っていたと言われたのも納得。うんうん、確かに言霊を感じるよ(´ー`)2018/10/21
しゅてふぁん
31
古代和歌。有名な和歌がたくさん紹介されているみたいだけれど、私には馴染みのないものばかりだった。枕詞の背後には神々に関わる伝承があり、心霊に関わる接頭語が使われている。そして、初期万葉の長歌は難解だった。ちゃんと日本語で書いてあって読むことは出来るのに、現代語訳を読まないと意味が全く分からない。不思議だ…。でも、贈答歌には、女性の返歌が強気なものが多くて楽しかった。伝承に基づいてうたわれたもの、伝承の中でうたわれたもの、といった解説が多かったのが印象的だった。2016/12/02
ゆずきゃらめる*平安時代とお花♪
29
〈熟田津に 船乗りぬと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出てな〉額田王。このほぼ奈良時代、彼女は宮廷女流歌人だった。けしてこの和歌は楽しい歌ではない。戦に向かう歌なのだと。白村江の戦いのために読まれた歌。彼女は本当にこんな歌を読みたかったのだろうか。2016/01/20
森の三時
23
男から「みこも刈る 信濃の真弓 我が引かば 貴人(うさひと)さびて 否と言はむかも」と詠めば、女から「みこも刈る 信濃の真弓 引かずして をはくるわざを 知ると言はなくに」、続いて「梓弓 引かばまにまに 寄らめども 後の心を 知りかてぬかも」と返している。このあたりは、万葉の贈答歌の楽しいところ。もちろん「茜草指す~」と「紫草の~」も。2017/02/11
-
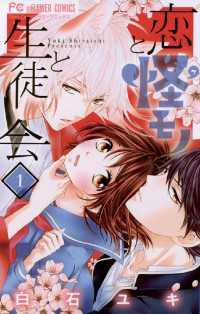
- 電子書籍
- 恋と怪モノと生徒会(1) フラワーコミ…