出版社内容情報
「たとえ法然上人にだまされて、念仏して地獄に落ちたとしても、まったく後悔することはない」。『歎異抄』に記された親鸞のこの言葉は、抽象的な理論よりも、具体的な人、その言葉のもつインパクトのほうがはるかに大きいことをよく表している。直接会うことのできない歴史上の人物でも、それぞれに迷い、苦しみながら救いを求め、道を切り拓いた人の生きざまや言葉は、私たちにダイレクトに訴えかける。本書は、時代と格闘しながら日本仏教を形成した名僧たち30人の軌跡(生き方)と残したことば(教え)で、仏教の教えに再入門する一冊。気鋭の比較宗教学者、釈徹宗氏の監修で、最澄=伝教大師1200年大遠忌を期して刊行する。
内容説明
「たとえ法然上人にだまされて、念仏して地獄に落ちたとしても、まったく後悔することはない」『歎異抄』に記された親鸞のこの言葉は、抽象的な理論よりも、具体的な人、その言葉のもつインパクトのほうがはるかに大きいことをよく表している。直接会うことのできない歴史上の人物でも、それぞれに迷い、苦しみながら救いを求め、道を切り拓いた人の生きざまや言葉は、私たちのダイレクトに訴えかけてくる。外来の鎮護思想として日本に伝わり、やがて独自の発展を遂げた日本仏教。僧侶たちは釈迦の教えを実践し、真理を説き、日本人の思想と倫理に大きな影響を及ぼした。時代と格闘しながら日本仏教の礎を築いた名僧たち30人の軌跡と残した言葉で、日本仏教に再入門する。
目次
スペシャルインタビュー 釈徹宗 この名僧の言葉がすごい!心と体をおだやかに整えてくれる仏教のことば
第1章 飛鳥・奈良時代―仏教の伝来と国家鎮護システム(聖徳太子―「日本の釈迦」になぞらえられる仏教流布の象徴;役小角―蔵王権現を感得し、「修験道の祖」とされる伝説の行者 ほか)
第2章 平安時代―二人の巨僧によって築かれた日本仏教の礎(最澄―比叡山に日本仏教の母山を築いた天台宗の開祖;空海―一代にして真言密教を日本に根づかせた稀代の天才 ほか)
第3章 鎌倉時代―貴族の仏教から民衆の仏教へ(法然―日本仏教にパラダイムシフトを迫った「専修念仏」の提唱者;明恵―釈迦に恋慕し、戒律を重んじた禁欲のカリスマ僧 ほか)
第4章 南北朝・室町時代―新仏教の普及と体系化の時代(夢窓疎石―七度に渡って国師の称号を賜った臨済宗の名僧;一休宗純―純粋孤高、天衣無縫、「風狂の詩聖」と呼ばれた反骨の傑僧 ほか)
第5章 江戸時代―寺と檀家、幕府の保護のもとでの繁栄(天海―徳川初期将軍三代の政策ブレーンをつとめた黒衣の宰相;沢庵宗彭―流罪にも負けず、三代将軍家光のブレーンになった反骨の禅僧 ほか)
著者等紹介
釈徹宗[シャクテッシュウ]
1961年大阪府生まれ。84年龍谷大学卒、89年龍谷大学大学院博士課程単位取得満期退学、01年大阪府立大学大学院人間文化研究科比較文化専攻博士課程修了、学術博士。専門は比較宗教思想、宗教文化。浄土真宗本願寺派・如来寺住職を務める一方、兵庫大学生涯福祉学部教授を経て、相愛大学副学長・人文学部教授に就任。日本宗教学会評議員。論文「不干斎ハビアン論」で涙骨賞優秀賞(第5回)、著書『落語に花咲く仏教』(朝日新聞出版)で河合隼雄学芸賞(第5回)、また仏教伝道文化賞・沼田奨励賞(第51回)を受賞している。著書多数。NPO法人リライフ代表、認知症高齢者のためのグループホーム「むつみ庵」を開設・運営(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- プリンセスくんとナイトさん~最強にカワ…
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢なので、溺愛なんていりません!…
-

- 電子書籍
- こちら大阪社会部【合本版】(2)
-

- 電子書籍
- RUDO Accessory Vol.…
-
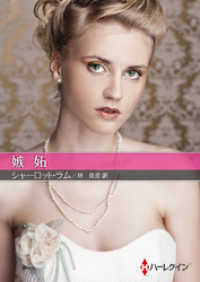
- 電子書籍
- 嫉妬【ハーレクインSP文庫版】 ハーレ…



