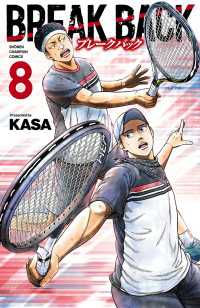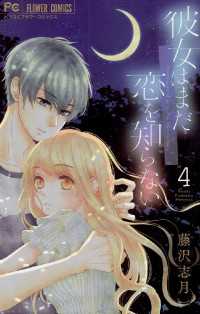出版社内容情報
すでに絶滅した古生物たち。
彼らも、私たち現生生物と同じように、怪我をしたり、病気になっていました。
そんな古生物の怪我や病気について研究するのが「古病理」というジャンルです。
古病理の研究者は、化石を丹念に調べて怪我や病気の痕跡を見つけ出し、
「古生物がどのような身体的悩みを抱えて生きていたのか」
という点を推理します。
本書は、そんな古病理について迫ってみました。
怪我や病気を患った化石画像をふんだんに掲載し、そこから見えてくる事実を、科学的にアプローチ。
さらに、怪我や病理を患った状態を、精細なイラストで復元します。
古病理から見えてくる「古生物が受けた身体的な悩み」には、いったいどんな世界が広がっているのでしょうか。
もしかすると、あなたの手元にある化石も、なにか特別な物語を秘めているかもしれませんよ。
目次
整形外科の章(欠損;外傷 ほか)
内科の章(カリフラワー;皮質の肥厚化 ほか)
呼吸器科の章(内側の突起物;気道が埋まる)
歯科の章(歯槽の膨らみ)
感染症科の章(最古の寄生虫?たち;孔・穴―寄生の痕跡 ほか)
著者等紹介
土屋健[ツチヤケン]
埼玉県生まれ。サイエンスライター。オフィス ジオパレオント代表。日本地質学会会員。日本古生物学会会員。日本文藝家協会会員。金沢大学大学院自然科学研究科で修士(理学)を取得(専門は地質学、古生物学)。その後、科学雑誌『Newton』の編集記者、部長代理を経て2012年より現職。2019年にサイエンスライターとして初めての日本古生物学会貢献賞を受賞。古生物学に関する著作多数
林昭次[ハヤシショウジ]
岡山理科大学 生物地球学部 恐竜学科 准教授。北海道大学大学院理学院博士課程修了。ドイツ・ボン大学でのポスドク研究員、大阪市立自然史博物館の学芸員を経て、2017年より現職。恐竜をはじめとする脊椎動物の骨組織を対象に、進化や生態の研究を行っている。近年は、化石骨組織の知見を現生動物に応用し、オオサンショウウオ、ケラマジカ、アマミノクロウサギなどの希少動物の生態を解明する試みにも取り組んでいる
唐沢與希[カラサワトモキ]
三笠市立博物館 学芸員。1986年長野県生まれ。2015年、京都大学博士課程単位取得退学。修士(理学)。2015年5月より現職。主にアンモナイト類の病理変異やタフォノミー(化石化過程)、化石オウムガイについて研究をするほか、三笠市立博物館に収蔵・展示されているモササウルス類化石であり、国指定天然記念物でもあるエゾミカサリュウ(タニファサウルス・ミカサエンシス)を用いた教育プログラムの開発なども行う
田中源吾[タナカゲンゴ]
熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 准教授。1974年愛媛県生まれ。島根大学理学部地質学科卒業後、静岡大学理工学研究科に進学。2002年博士(理学)取得(静岡大学)。日本学術振興会特別研究員、レスター大学研究員、京都大学理学部研究機関研究員(講師)、群馬県立自然史博物館主任学芸員、海洋研究開発機構研究技術専任スタッフ、熊本大学合津マリンステーション研究員、金沢大学国際基幹教育院助教を経て現職。専門は層位・古生物学。特に、節足動物化石を用いた機能形態学や古環境学
冨田武照[トミタタケテル]
沖縄美ら島財団総合研究所 動物研究室 主査研究員/水族館管理センター 魚類課兼務。1982年生まれ。東京大学大学院博士課程修了。北海道大学総合博物館、カリフォルニア大学デービス校、フロリダ州立大学沿岸海洋研究所での博士研究員を経て、現職。サメの機能形態学、形態進化学を専門とする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
たまきら
フク
Go Extreme
gachin