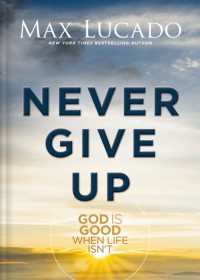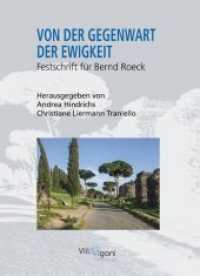出版社内容情報
「もっとデータを活用して業績アップ」
「データドリブンで事業をもっと大きく」
このようにデータが重要といわれる現代では、一人一人がデータとの向き合い方を会得し、自分自身の意思と判断力を持つために「データリテラシー」を身に付けることが必要です。
データリテラシーとは、データ活用の意味から理解し、人間がデータとどう向き合うのかという視点で、どのような役割を担う人にとっても今必要なデータにまつわる知識です。データベースやSQL、難しいシステム、あるいはデータを可視化するデザインの話だけではありません。
本書は、著者が創設した「Tableauブートキャンプ」における師と弟子の対話を元に、8年間かけて会得したノウハウ・考え方をまとめあげた本です。
「データとはなにか」
「データを使ってどのように改善するのか」
「データを可視化して人々を動かすにはどうすればよいか」
これらの観点から、技術的な専門知識だけではない、データ活用の本質を考えます。
内容説明
データウェアハウスとBIツール、基幹系システムと情報系システム、分析プラットフォーム、ストーリーテリング、ビジュアル分析…増え続けるデータを正しく理解し、伝え、データ活用を加速する。Tableau DATA Saberの創始者が語る究極の「データリテラシー」。
目次
0 データドリブン文化のはじまり
1 データストーリーテリング
2 ビジュアル分析
3 分析プラットフォーム
4 データとはなにか
5 データドリブン文化をさらに広げるために
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶう
12
Tableau伝道師であるKT氏の著書。データ活用の初心者である弟子が師匠との対話を通じてデータドリブンとは何か学んでいくといった内容。Tableauの詳細な使い方の説明は載っていないので、単純にツールの操作方法を学びたい人は他のTableau本を買ったほうがいいだろう。ビジュアライゼーションでの色の使い方であるとか、効果的な見せ方のコツなど、どのBIツールを使う時でも共通するノウハウが本書からは学べる。データドリブンにはストーリーを作る部分が極めて重要。なぜなら人は腹落ちして初めて動くのであるから。2021/10/27
山のトンネル
5
0流し読み。前半は大学のレポート提出における体裁を指南するような形で、データのビジュアル化などについて触れつつ、後半は社内でどのようにデータを活用していくかなどの応用に触れる(ダッシュボード、BIツールetc...)。著者は初心者が1章ずつ本書を読み込むことで、読了後には彼らのデータリテラシーが高まることを想定していると思われるが、具体的にどんな初心者をターゲットにしているのかが不明である。day1、day2を読む限りかなり初心者を想定しているのだろうが、個人的には前半がややボリューム過多な印象を受ける。2022/04/07
さくら
3
Data saberの最終試験対策に読んだ。最終試験に関するヒントが盛りだくさんなので、Data Saberを目指している人は読んでおいた方がいい。Dataを使ってプレゼンをするのならストーリーを作成することが大事、データドリブンを実現させるためには、必ずしも、社員全員がBIツールを使う必要はないとのこと。2025/01/08
anco
2
データ・ドリブン文化とはデータがもたらす拡張経験を自分のものとし、自らの間を研ぎ澄ませて意思決定を下す人々による極めて人間中心の文化。32, 34, 40, 79, 101, 109, 131, 222, 232, 239, 296, 315, 328, 3352023/07/07
Yusuke Nakamura
1
ツールの話のみに落ちる事なくデータドリブンとは?データ活用していくにあたり、周りを巻き込むにはどうしていけば良いのか分かりやすく書かれており良書。 2023/07/05