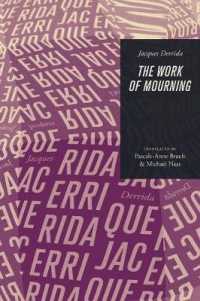出版社内容情報
技術が進むにしたがって、コンピュータの中身が見えなくなってきています。コンピュータの頭脳としてCPUがあって、OSがあってプログラムが動く…。漠然とわかっていても、実際にどういうしくみで意図したとおりに動作しているのかとなると、なかなかイメージできないものです。本書はこのように、ブラックボックスになっているコンピュータのしくみを、「炙る」「揚げる」などの過激な手法も用いつつ、半導体レベルから実際に目に見える形でひもといていきます。
内容説明
基板を揚げて、部品を炙って、半導体の中まで覗いて理解を深めよう。
目次
第1章 ソフトウェアとハードウェアの世界の境界
第2章 ソフトウェアから近づいてみる
第3章 ハードウェアから近づいてみる
第4章 揚げて炙って中身を覗く
第5章 取り出したチップを解析してみる
第6章 コンピュータの再構成
第7章 物理世界とコンピュータとの界面
著者等紹介
秋田純一[アキタジュンイチ]
1970年名古屋市生まれ。東京大学博士課程修了。公立はこだて未来大学を経て、金沢大学教授。専門は集積回路(特にイメージセンサ)と半田付け、およびそれに関連して、「無駄な抵抗コースター」ほかMakerとして活動する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
32
技術が進むにしたがって中身がブラックボックスと化してきたコンピュータ。そのしくみを「炙る」「揚げる」などの過激な手法も用いつつ、半導体レベルから実際に目に見える形でひもといていく一冊。大規模化・複雑化しハードウェアとソフトウェアが分離してブラックボックス化が進んでいるのに、仕組みを知らないままでも普通に使えてしまっている現状や、加速度的に進んだ集積回路の小型化、それに伴い小型化した機器ではどこでどう処理を分担しているのか、半導体チップを炙ったり揚げたりで分解して解説してゆく様子はなかなか興味深かったです。2020/09/13
ようへい
16
この世の理が明らかにされるにしたがって、あらゆる物事が細分化され、複雑化している。それはつまり、庶民にとって世の中がブラックボックス化しているという事を示している。スイッチを押すと電源が入り、アプリなどにデータを入力すると答えが返ってくる。便利に世の中は複雑な計算の上に成り立っているのに、その過程が全く見えない。これは複雑な社会情勢を過度に単純な枠組みで説明するという陰謀論に似ている。パソコンって一体何なんだろう。いや、そもそも電気って何なの?と、ドツボに嵌る。Lチカ、やってみたい。2024/02/14
ももいろ☆モンゴリラン
2
極文系(私のことです)でも読めました。第6章は少し辛かったけど…コンピュータが複雑になりすぎて、誰も全容がわからないなんて想像してなかった。システム課は知ってるものと思ってた。いつもトンチンカンな質問してごめんなさい… 揚げて炙って、というのは誇張した表現かと思ったら実際にそうしないと内部がわからないのね。 「論理回路」面白そう。2024/08/12
とみぃ
2
★★★☆☆ 金沢大の秋田教授により、MOSFETレベルからコンピュータがどのように構成されるのかについて優しく解説されている。書籍名が独特で好きなのだが、前述内容について解説された後に、油を使って200度近くで基板を揚げることで半田を融解してチップを取り外し、炙ることでパッケージ樹脂を炭化させて内部チップを観察するという内容からきている。コンピュータのしくみについて解説した書籍は大量にあるが、初心者にとって概要を掴みやすい良い本だと感じた。最後の書籍紹介と集積回路設計・製造の民主化については興味深かった。2023/08/28
takao
2
文字通り2022/11/13
-

- 洋書
- Öko-Bürge…