出版社内容情報
ラズパイ電子工作で生成AIをどう使う?
外部グラボをラズパイ5に接続して動かす!
テキストやドキュメント、プログラミング、画像、動画など、今やありとあらゆるデジタルコンテンツが「生成AI」で制作できる時代になった。そんな生成AIは、ラズパイや電子工作にとっても有益なツールになり得る。ラズパイの設定方法やトラブル解決、電子工作での接続方法、プログラミング作成など、これまでは自分で調べたり作成したりする必要があった作業が、生成AIに質問するだけで解決できるようになったからだ。特集1では、そんな生成AIの活用方法を4つのパターンに分けて紹介する。
電子工作の基本は、「どういった電子パーツがあって」「それらをプログラムでどう制御するのか」を理解することにある。特集2では、主要な電子パーツの「つなぎ方」と「制御方法」を、ステップアップ方式で解説している。
特集3と特集4では、マイコンボード「ラズパイPico」で電子工作を始めるための入門記事をまとめた。特集3はPython、特集4はC言語を使って作品を制作するための方法を解説する。
ラズパイの最上位機種である「ラズパイ5」では、ラズパイとして初めて、拡張インタフェースの「PCIe x1」が搭載された。そこで特集5では、同じPCIe規格である外部グラフィックスカードを実装し、実際に動かすことができるのかを検証してみた。
特集6では、ラズパイの買い方からOSのインストール方法、初期設定や基本的な使い方、さらには電子工作に必要な環境構築の手順などをまとめた。ラズパイが初めての人は、まず最初に目を通してほしい。
【目次】
≪目次≫
【特集1】ラズパイではじめる AI活用入門
・Part1
ラズパイの使い方からプログラム作成まで
ChatGPT&Gemini 生成AIの活用方法
・Part2
大規模言語モデル(LLM)をラズパイで動かす
自分専用の生成AIマシンを構築
・Part3
音声認識もAIを使えば誤認識を減らせる
faster-whisperで音声をテキスト化
・Part4
AI処理プロセッサ搭載の周辺機器が登場
物体認識を高速に処理
【特集2】「つなぎ方」と「制御方法」のキホン 主要電子パーツ入門
・準備編
電子工作をはじめる最初の一歩
プログラムの作成環境を整える
・入門編
電子パーツを動かす「電気」を理解
まずは乾電池だけで動かしてみる
・Part1
GPIOの電圧を切り替えてLEDを制御
スイッチの状態も読み取ってみよう
・Part2
外部電源でパーツを動かそう
トランジスタやドライバーを活用
・Part3
LEDの明るさを変化させてみよう
PWMで疑似的に中間状態を生成
・Part4
加速度センサーの値を取得しよう
I2Cで電子パーツとデジタル通信
・Part5
アナログ出力の温度センサーを使おう
ADコンバーターがアナログ値を変換
・Part6
サーボモーターを制御してみよう
PWMのパルス幅で回転角度を指定
・Part7
小さな画面に文字や図形を表示
有機ELディスプレイを使ってみる
・応用編
「フルカラーLED」「光センサー」「人感センサー」
人気パーツ3種を動作させよう
【特集3】Pythonでプログラミング Picoで電子工作入門
【特集4】C言語でプログラミング Picoでベアメタル開発入門
・Part1
ラズパイPicoが実装するマイコン製品
RP2040の仕様や特性を知ろう
・Part2
公式C SDKはVSCode拡張機能として提供
ベアメタル開発の環境を構築しよう
・Part3
ソースコードの作成からビルド、デバッグまで
Lチカで開発の流れを把握しよう
【特集5】ラズパイ5のPCIeで機能強化 高性能グラフィックスカードをつなぐ
-
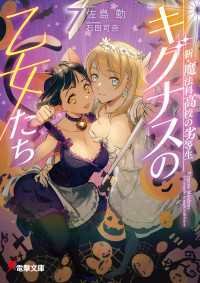
- 電子書籍
- 新・魔法科高校の劣等生 キグナスの乙女…
-

- 電子書籍
- レディは陰の実力者【タテヨミ】第35話…






