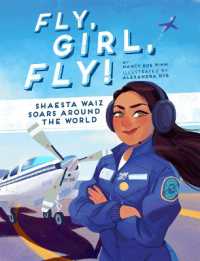出版社内容情報
■ネットワークやデジタルデバイスの高度化で、企業には膨大なデータが蓄積されるようになってきた。この膨大なデータを「資産」として活用できないか、事業化できないかというニーズから「データマネタイゼーション」の取り組みが注目されている。
■多くの企業が社内にデータを保有している現在、データマネタイゼーションのチャンスは、業種や規模を問わず幅広い企業に広がっている。とはいえ、一言でデータマネタイゼーションといっても、具体的なイメージが湧かなかったり、自社に当てはめた際に、様々な疑問が頭をよぎるケースもありそうだ。
「虎の子」であるはずの自社データを社外に売ってしまって、本当に大丈夫なのだろうか。
そもそも社内に分散するデータのすべてを一元的に把握するのは不可能ではないのか。
データは自社の製造や取り引きに特化した形式で作っており、見直しに必要なお金や手間に見合うメリットはあるのか。
どんな組織や人員を担当に据えれば良いのか。
仮にデータビジネスを新事業として展開する場合、既存の事業とのすみわけはどうすべきか。
サービス利用者のパーソナルデータをマネタイズしたいが、個人情報保護規制の厳格さが増すなかでサービスをどう設計すべきか。
実際にデータを販売するとして、売り先をどのように見つければ良いのだろう。
いったい何をどこから、どのように手をつければ良いのか見当もつかない――。
■本書では、こうした多くの疑問にこたえる実践的な解説を試みた。取り巻く環境の著しい変化に対応し、最新の潮流や事例も多く紹介している。
これまでデータマネタイゼーションの書籍は特に海外で多く出版されてきたが、日本ではあまり増えてこなかった。データマネタイゼーションの普及には、そうしたノウハウの共有や浸透が不可欠と考えて、本書では実際に準備や導入、運用を進めるうえで役に立つ情報を、できるだけ平易な表現かつ幅広い観点で紹介する。
内容説明
あなたの会社や組織には、存在があまり知られないまま保管・蓄積され続けているデータがないだろうか。顧客との取引記録や従業員に関する情報、製造設備の検査結果、マーケティングの効果測定―あらゆるモノがネットにつながる「IoT」機器が生み出す大量のデータなども加わり、企業が蓄積するデータは今この瞬間も増え続けている。これら「埋もれたデータ」を掘り起こして新たな加工や分析を加えることで、新たな企業の「資産」として課題解決や成長に結びつけることは可能だろうか―。答えはイエスだ。多様な企業規模や業態で広がるビジネスチャンスの最新潮流と事例を紹介。データで稼ぐ!
目次
第1章 データマネタイゼーションの実像(データマネタイゼーションとは何か;主な事例と「3つの観点」 ほか)
第2章 データマネタイゼーションの点検(社内にはどんなデータがあるのか;データからインテリジェンスへ ほか)
第3章 データマネタイゼーションはいろいろ(既存事業の延長か、新規事業か;新規事業としてのデータマネタイゼーション ほか)
第4章 データマネタイゼーションを成功に導く(マネタイズ虎の巻「見えてきた勝ちパターン」)
第5章 方法論としてのデータマネタイゼーション(5段階で進めるデータマネタイゼーション;(アイデア抽出フェーズ)アイデアをリストアップ ほか)
著者等紹介
三木朋和[ミキトモカズ]
日本経済新聞社情報サービスユニット上席担当部長。早稲田大学理工学部卒。1994年日本経済新聞社入社後、約30年間にわたり一貫してデータに関わる。データバンク局、証券部(記者・デスク)で企業財務や証券市場の取材・データ分析を担当。2019年4月に開始したデータジャーナリズムの連載「チャートは語る」を企画。2021年データ報道グループ長。2023年から情報サービスユニット上席担当部長としてデータビジネスを担当
天野秀俊[アマノヒデトシ]
株式会社クニエ新規事業戦略チームシニアマネージャ。早稲田大学大学院理工学研究科修了。外資系コンサルティングファームへ入社し、製造業のサプライチェーンマネジメントを主軸とした数々のDXコンサルティングに従事。2009年よりクニエにて、通信・製造/流通・ヘルスケア・農業・教育等の様々な業界における新規ビジネス企画に従事。2021年にデータマネタイゼーション専門部隊を立ち上げ、コンサルティングサービスの提供、講演を多数実施(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 2025年受験用 全国大学入試問題正解…