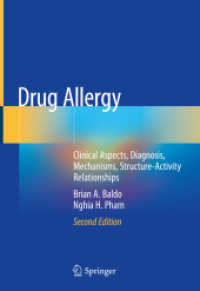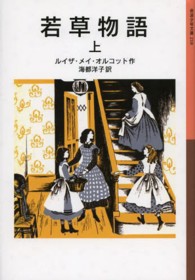出版社内容情報
●データに基づき、最適行動・施策を考える
「子どもの教育」というと、親が自分の経験値で語ったり、周りの情報を鵜呑みにして行動してしまうもの。そういった「思い込み」を排し、根拠に基づいた論理的分析で結果を導くために、経済学を活用する。現在、様々なデータを入手することが可能になり、企業などでもエビデンスベースで課題解決をするケースが増えている。教育現場でもこのデータをもとにした議論が活発化している。
・多くのデータが積み上がり、日本でのデータや分析事例も増えてきた。海外の研究はもとより、本書は日本の分析も多くあるのが特徴。
・コロナ禍によって、家庭学習やICT教育が増えた。その影響などについて、可能な限り分析を試みている。
「学歴はデータ的に優位なのか」「家庭の役割はどれだけ必要なのか」「ゆとり教育は有効だったのか」など、読者の興味に適う内容。
内容説明
教育の効果を高めるためには、お金がかかります。どのような教育投資が成功に結びつくのか、制度やインセンティブをどのように設計するのが最適なのか。経済学の視点から論理的に解説します。著者は大学で教鞭をとる経済学者で、統計データに基づく分析を行うなど精力的に活動しています。家庭の役割や、学校教員のインセンティブ、教育制度の視点など、総合的な視点から解説しています。最終的には日本の発展のためにどうするのが最適なのかという幅広い視点からも解説します。自分の子どもを教育機関に預ける親世代はもちろんのこと、学校教員や教育の制度設計にかかわる人まで、幅広い読者が対象となります。
目次
第1章 教育への投資のリターン(人的資本理論;人的資本とシグナリング;教育のリターンを計測する方法;認知スキルと非認知スキル)
第2章 スキル形成のための学校と家庭の役割(教育の生産関数という枠組み;スキル形成における家庭の役割;経済格差と教育格差;政策やショックとの関係)
第3章 学校の仕組みを経済学で考える(学級規模(クラスサイズ)
ピア効果
先生の重要性)
第4章 様々な教育政策の評価(ゆとり教育;学校間競争;奨学金;就職)
第5章 社会の変化への対応と教育(日本経済の現状と課題;技術革新(ICT、AI)と労働市場と教育
教育におけるジェンダーの問題
海外と日本
高齢化社会)
著者等紹介
佐野晋平[サノシンペイ]
神戸大学大学院経済学研究科准教授。1979年生まれ、山口県出身。2001年東京都立大学経済学部卒業。2006年大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了(博士(経済学))。日本学術振興会PD、神戸大学准教授、千葉大学法政経学部准教授などを経て、2020年より現職。専門は教育経済学と労働経済学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おせきはん
koji
icon
みかん。
Cana.t.kazu
-

- DVD
- ふらいんぐうぃっち Vol.3