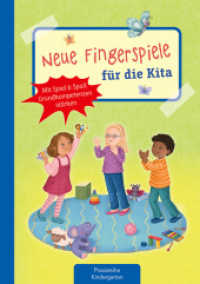出版社内容情報
ウクライナ侵攻は、「冷戦終結以降、このような戦争はない」と思い込んでいた世界に大きな衝撃を与えたが、台湾有事や北朝鮮の問題などもあり、日本の国防政策のあり方も再考を迫られている。このような状況のなか、昨年末、政府は防衛費(対GDP)を倍増することを決め、2023年度から5年間の総額を43兆円程度とすることを閣議決定した。
しかしながら、現在進行中の国際秩序の変容の先行きを考えた場合、国防政策の問題は財源のみの問題ではない。急速な人口減少が進むなか、不足する自衛隊員の問題をどうするか、核の問題にどう向き合っていくのか等の問題の整理も行う必要がある。そこで、本書は鹿島平和研究所で開催されている「国力研究会」「秋山研究会」のメンバーが中心となり、元防衛次官であった秋山昌廣氏をリーダーとして17の論点について整理し、世に問う。執筆者は下記の通り。
小黒一正(法政大学教授)、徳地秀士(政策研究大学院大学シニアフェロー)、髙見澤將林(元国家安全保障局次長)、神保謙(慶應義塾大学教授)、小原凡司(笹川平和財団上席フェロー)、細谷雄一(慶応義塾大学教授)、関山健(京都大学准教授)、岩本友則(日本核物質管理学会事務局長・日本原燃㈱フェロー)、西山淳一(元三菱重工業、未来工学研究所研究参与)、松村五郎(元東北方面総監)、土屋大洋(慶応義塾大学教授)、森聡(慶應義塾大学教授)
内容説明
タブーを恐れず正面から問題提起。自衛隊員不足、財源調達から台湾有事、経済安全保障、自衛隊関連法制の再構築まで、重要課題を多くの専門家が論じる。「鹿島平和研究所プロジェクト」を書籍化。
目次
論点1 不足する自衛隊員の問題にどう対処するか
論点2 有事の財源調達をどうするか
論点3 核抑止の問題や軍備管理・軍縮にどう対応すべきか
論点4 核シェアリングと拡大抑止において日本の選択肢はどうあるべきか
論点5 台湾有事や尖閣占拠にどう対処するか
論点6 日米同盟はどのように強化すべきか
論点7 日欧、諸外国との安全保障協力の充実にどう対応するか
論点8 平時や有事でのエネルギー資源・食料の調達をどうするか
論点9 核兵器攻撃と原子力施設への軍事攻撃にどう備えるか
論点10 防衛産業をどう育成するか(日本版DARPA構想)
論点11 国家安全保障を支えるために、国民にはどのような意識が必要か
論点12 宇宙・サイバー・電磁波領域をどう防衛するか
論点13 気候変動による施設・装備・運用への影響にどう対処するか
論点14 先端技術を防衛にどう活かすか
論点15 日本のインテリジェンスは必要十分か
論点16 経済安全保障において経済と安全はどのようにバランスをとるべきか
論点17 自衛隊をめぐる関連法制はどのように再構築されるべきか
著者等紹介
秋山昌廣[アキヤママサヒロ]
元防衛事務次官、安全保障外交政策研究会代表、鹿島平和研究所顧問。東京大学法学部卒(1964)、大蔵省入省、大蔵省大臣官房審議官。防衛庁防衛局長、防衛事務次官(1997)。ハーバード大学客員研究員(1999)、政策研究大学院大学特任教授、立教大学21世紀デザイン研究科特任教授、北京大学国際関係学院招聘教授。海洋政策研究財団会長、東京財団理事長(2012)
小黒一正[オグロカズマサ]
法政大学経済学部教授。一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了(経済学博士)。1997年大蔵省(現財務省)入省後、大臣官房文書課法令審査官補、関税局監視課総括補佐、財務省財務総合政策研究所主任研究官、一橋大学経済研究所准教授などを経て、2015年から現職。財務省「財政制度等審議会・財政制度分科会」委員、日本財政学会理事、鹿島平和研究所理事、東京財団政策研究所研究主幹(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ohe Hiroyuki
Ra
お抹茶