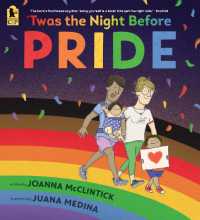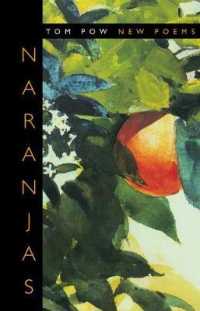出版社内容情報
●半世紀ぶりの大インフレ、四半世紀ぶりの円安
コロナ禍とウクライナ戦争を背景におよそ半世紀ぶりの大インフレが世界を襲った。低インフレにあえいできた日本も例外ではない。「輸入インフレ」の深刻度は米欧をしのぐ。資源高に根ざす物価高に拍車をかける円安が同時に広がったためだ。世界的なインフレの波のなかでも、日本は賃金デフレの流れが終わらず、日銀は金融引き締めに動けない。輸入インフレと、なお残る賃金デフレ。そのダブルパンチが通貨安を生み、さらなる物価高を生む悪循環になった。
本書は、日本と海外に広く目を向け、市場をウオッチしてきたベテランの日経記者によるもの。ファクトを積み上げ、幅広い取材から総合的な視点で日本の今後を占う。
●ピンチはチャンスになるか
苦境の日本にチャンスはあるか。モノの値段が上がるということは、停滞してきた日本経済を動かすことになる。よい値上げはモノやサービスの付加価値をあげることであり、脱炭素、デジタル時代においてのより一層のイノベーションが期待できる環境となる。例えば物価連動の賃金制度を取り入れるなどして、消費者の効用をあげるという策も必要だ。
また、4月からの日銀新総裁の就任は、脱アベノミクスを掲げたものになる必要があるだろう。円安誘導で企業業績は向上したものの、賃金は下落し、格差は助長された。今後も資源インフレが予想されるなかでの円安は、もはや限界を迎えている。正常な金融政策を取り戻し、成長に向けて舵を切っていくことが求められる。
内容説明
コロナ禍、ウクライナ紛争を経てインフレはさらに加速した。物価も金利も賃金も、ずっと動かないことが当たり前だった日本が変わろうとしている。この構造を丁寧に調べ上げ、明日への処方箋を探すための1冊。
目次
プロローグ あなたが手にした品物の値段から世界がみえる
第1章 日本の物価に何が起きたのか
第2章 「インフレ」ゆえに「デフレ」が深まる不思議の国
第3章 「景気を思う」ゆえに「景気を冷やす」?円安のジレンマ
第4章 最終兵器「黒田日銀」の終幕円相場はどこへ
第5章 パウエルFRBの正念場名議長か黒歴史か
第6章 賃金は上がるか「失われた30年」打開への道
第7章 世界インフレ時代、「終わり」か「始まり」か
第8章 「ピンチをチャンスに」6つの提言
著者等紹介
大塚節雄[オオツカセツオ]
日本経済新聞社編集委員兼論説委員。1971年生まれ。1994年早稲田大学政治経済学部政治学科卒、日本経済新聞社入社。編集局証券部、長野支局などを経て2001年経済部。主に日銀の金融政策や金融市場の取材を担当した。その後、日本経済研究センターで景気予測業務に従事し、札幌支社編集部では夕張市の財政破綻も取材した。2013年以降、経済部次長兼編集委員、米ワシントンのブルッキングス研究所の客員研究員などを経て2016年から米州編集総局編集部(ニューヨーク)。主に米国の金融市場や金融業界について取材・報道した。2019年国際部次長・副部長を経て2020年4月に新設の「専門エディター」(金融政策・市場担当)としてグローバル市場や内外の金融政策の動向について取材・報道。2023年4月から現職。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
壱萬参仟縁
ゼロ投資大学