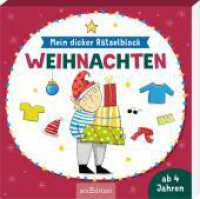出版社内容情報
役職定年の普及によって日本人の給与は55歳頃から減少する時代になった。70歳定年になっても60歳以降の収入はさらに激減する。しかし、その頃から子供が大学に行って教育費がピークとなる一方、親の介護が始まる。将来が見通せない時代にあって、30代で期間35年の住宅ローンを借りて、最後まで返しきれるのかという老後返済不安がこれまでになく高まっている。
人生100年時代、定年後に引退して悠々自適の生活を送れる人は稀。働けるうちは働き続ける時代にあっては、壮年期を過ぎたら、転職・起業・再教育・住みかえといったライフチェンジを考えることがむしろあたり前となる。このとき重荷になるのが家とローン。
60歳以上の日本人にとって「自己居住住宅」は全財産の5割超を占める最大の「資産」。しかし、人生100年時代にあっては、親が子供に家を相続させるころには子供は60代。もう必要のない家は空家予備軍となるのみ。また、2045年頃には3割近く人口が減るとされる時代に都心等ごく一部の場所を除けば土地は値下がりこそすれ、値上がる可能性は低い。こうしてみると、老後に住み続けるしかない家は「相続財産」や「資産」ではない。
このように、庶民が漫然と「期間35年の住宅ローンを借りて家を買う」ことには、大きなリスクが生じている。そして、この背景には欧米にはない上記のような「特殊日本的」要因が非常に大きい。
筆者は、こうしたわが国固有の「住宅ローンの問題」を解決するために、15 年前に大学発ベンチャーとして、マイホームの借上げ行う非営利機関(JTI)を公的支援を受けて作り、政府の公費補助事業を通じて資金を確保し、新しい住宅金融の技術開発とそのためのリスク管理に必要なデータの蓄積を行ってきた。こうしたできあがったのが JTI の公的借上げ制度により実現できる価値をもとにした住宅の将来価値保証(残価保証)と、これを活用した残価設定型住宅ローンである。
本書は、注目されているが手ごろなガイドがまだない残価保証や残価設定型住宅ローンの仕組みを一般の読者に分かりやすく説明するとともに、それが、住宅産業や住宅金融にどのような革命的意味を有するか、また、今後この仕組みを認定長期優良住宅一般に広げるために何が必要かについて論じる。
内容説明
役職定年の普及によって日本人の給与は55歳頃から減少する時代になった。70歳定年になっても60歳以降の収入はさらに激減する。しかし、その頃から子供が大学に行って教育費がピークとなる一方、親の介護が始まる。将来が見通せない時代にあって、30代で期間35年の住宅ローンを借りて、最後まで返しきれるのかという老後返済不安がこれまでになく高まっている。人生100年時代、定年後に引退して悠々自適の生活を送れる人は稀だ。働けるうちに働き続ける時代にあっては、壮年期を過ぎたら、転職・起業・再教育・住みかえといったライフチェンジを考えることがあたり前となる。このとき重荷になるのが家とローンだ。本書は、こうした「住宅ローンの問題」を解決するために、開発された残価保証と残価設定型住宅ローンの仕組みを、開発者自らが分かりやすく解説。
目次
第1章 住宅ローンは借金ではない?
第2章 残価設定型住宅ローンって何ですか?
第3章 なぜ、残価設定型住宅ローンなのですか?
第4章 残価設定型住宅ローンについてより詳しく教えてください
第5章 何年も先の住宅の価格を保証できるのはなぜですか?
第6章 残価設定型住宅ローンの利用例
第7章 住宅ビジネスや住宅金融のあり方はどう変わるでしょう?
著者等紹介
大垣尚司[オオガキヒサシ]
1959年京都市生まれ、82年東京大学法学部卒業、85年米国コロンビア大学法学修士。日本興業銀行、興銀第一フィナンシャルテクノロジー取締役、アクサ生命保険専務執行役員、日本住宅ローン社長、立命館大学教授を経て、青山学院大学教授・金融技術研究所長。博士(法学)。一般社団法人移住・住みかえ支援機構代表理事、一般社団法人日本モーゲージバンカー協議会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。