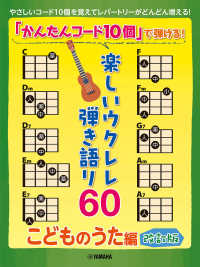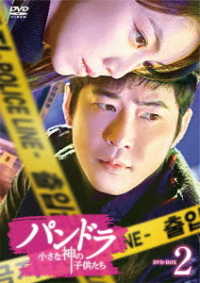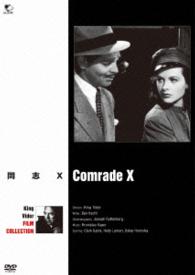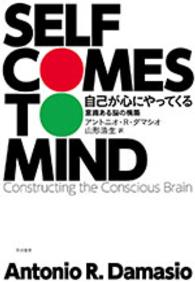出版社内容情報
■80年代の金融自由化から、金融庁による検査の時代、対話型への転換まで、40年間にわたる地銀史をキーパーソン二人が明かす。一人は大蔵省の護送船団行政の原体験をもち、金融庁長官として「金融処分庁」を「金融育成庁」に変える大転換を実行した遠藤俊英氏。もう一人は、広島銀行に30年間勤務したのちに異例の抜擢で金融庁に転じ、歴代長官を支えた日下智晴氏。実体験を通して、地銀と行政の実相を描く異色の金融史。
■大蔵省から地銀に転じた橋口収氏のエピソード、金融の専門人材が不足していた大蔵省、金融自由化に翻弄された地銀、銀行を恐怖に陥れた行き過ぎた金融検査の実態、金融庁が歴代長官のもとでどのように改革に取り組んだのかなど、当事者ならではの視点で率直に語る。
内容説明
80年代金融自由化からバブル崩壊を経て、恐怖の金融庁検査、対話型への転換、地域金融の再定義まで、40年間にわたる地銀史をキーパーソン二人が明かす。一人は大蔵省の護送船団行政の原体験をもち、金融庁長官として「金融処分庁」から「金融育成庁」への大転換を実行した遠藤俊英。もう一人は、広島銀行に30年間勤務したのちに金融庁に転じ、歴代長官を支えた日下智晴。役所と銀行の生々しい現場体験をもとに、地銀と行政の実相を描く異色の金融史。
目次
はじめに 地銀を監督する意味
序章 今、『地銀改革史』を書く理由
第1章 金融自由化の時代―「新人類」が見た風景
第2章 金融処分庁の時代―地銀と20年論争
第3章 金融育成庁の時代―金融庁の試行錯誤
第4章 金融共創の時代―地銀の理想と現実
第5章 金融挑戦の時代―試される信用創造機能
第6章 座談会 金融庁模索の時代―命令から対話へ
おわりに 地銀も「株主ガバナンスの時代」に
著者等紹介
遠藤俊英[エンドウトシヒデ]
1959年、山梨県生まれ。山梨県立甲府南高校卒業後、東京大学法学部を経て、1982年、旧大蔵省に入省。84年、ロンドン大学に留学。88年、米子税務署長を務めた後、国税庁国際業務室を経て、90年から2年間の銀行局銀行課勤務(課長補佐)で、金融行政に初めて携わる。主税局、IMF(国際通貨基金)を経て、2002年に金融庁証券取引等監視委員会特別調査課長として再び金融行政に戻る。14年に検査局長、15年に監督局長を歴任後、18年から第10代長官を務め、20年に退官する。23年6月から株式会社ソニーファイナンシャルグループ代表取締役社長兼CEO
日下智晴[クサカトモハル]
1961年、広島県東広島市生まれ。私立修道高校卒業後、神戸大学経営学部会計学科を経て、1984年、広島銀行に入行。総合企画部担当部長、融資企画部長、大阪支店長、リスク統括部長を歴任、2015年10月、広島銀行を退職し、金融庁に移籍する。監督局の地域金融企画室の初代室長のほか、検査局の地域金融機関等モニタリング長や事業性評価モニタリング室長を兼務したほか、監督局の地域金融生産性向上支援室長や地域課題解決支援室長も務め、地域金融の改革に尽力した。21年9月に定年で退官。祖父が開設した日下企業経営相談所を再興し、代表を務める22年6月から商工組合中央金庫社外取締役
玉木淳[タマキジュン]
1975年、神奈川県藤沢市生まれ。神奈川県立光陵高校卒業後、慶応大学経済学部を経て、1999年、日本経済新聞社に入社。流通経済部に配属後、2002年からの浦和支局勤務で旧あさひ銀行を担当し、金融取材を本格的にスタート。05年、金融庁クラブに移動し、20年間、ほぼ一貫して金融行政、金融ミクロ取材を続ける。20年、金融プロ向けデジタル専用媒体「NIKKEI Financial」の創刊に携わる。21年4月から金融エディター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
スプリント
Hiroo Shimoda
Takateru Imazu
めぐりん
-

- 電子書籍
- バラッド×オペラ【タテスク】 Chap…