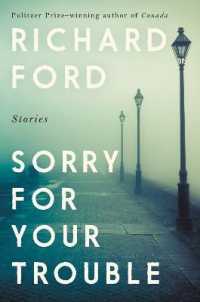出版社内容情報
歴史を通じて、並外れた強力な軍隊が出現することがあった。カエサルの時代のローマ軍、チンギス・ハーンの時代のモンゴル軍、ナポレオンの時代のフランス軍、これらはいずれも戦闘組織として抜群であった。
規模の制約を前提とすると、軍事的手段としての軍の価値は、「戦闘力(Fighting Power)」×装備の質と量となる。戦闘力は精神的、知的、組織的な基盤に依拠している。これは、規律と団結力、士気と主導権、勇猛さと頑強さ、戦闘意欲と必要ならば死ぬ覚悟といったものを様々に組み合わせた形で体現される。つまり、軍を戦闘へと駆り立てる気質の総体として「戦闘力」は定義できる。
戦争の兵器と手法は変化するが、戦闘力の本質は不変である。上に掲げた個々の資質の比重は時代によって変化するかもしれないが、資質自体は二〇〇〇年前のカエサルが率いた熟練兵であっても、現代とほとんど変わりはない 。戦闘力の欠陥はある程度は優れた装備品で補えるかもしれないが、戦闘力を欠く軍は脆弱な手段でしかない。表向きは精強で優れた装備を誇る軍であっても、端的に戦闘力がなかったがゆえに戦闘の最初の衝撃で崩壊した事例が歴史にはあふれており、それは近年でも例外ではない。これは企業の組織力にも当てはまる。
戦闘力の秘密には何が潜んでいるのであろうか。本書は、賞賛に値する水準まで戦闘力を発展させた歴史上の組織である、第二次世界大戦のドイツ陸軍に着目して、同時期のアメリカ陸軍と比較して戦闘力の根源に迫る。
本書は、軍事戦略の聖典とされている『戦争論』の著者クラウゼヴィッツの批判者であり通説に真っ向から立ち向かう(そして正論でもある)事で知られる、現代の第一級の軍事研究家クレフェルトが1992年に著した知られざる名著。ドイツ陸軍の強さは様々なエピソードで伝えられているが、それを初めて科学的に解明した挑戦的な書。ドイツ陸軍の強さをその民族性にあるとする俗説を論破し、組織文化、組織風土と言った曖昧な概念に逃げることなく徹底的にファクトにもとづいて解明する。その鋭い分析は早稲田大学沼上教授もかねてから高く評価し、今回解説を執筆している。
組織運営、リーダーとなる人材の学歴、育成、選抜、指揮における権限の範囲、師団の構成、モチベーションなどを、社会学、文化人類学、心理学などの手法も駆使して詳細に分析。その内容はかつてない精度であり、このアプローチはあらゆる組織分析の手本となるものだ。ドイツ陸軍とアメリカ陸軍の戦闘力を数値化して比較することにも成功している。
内容説明
強さの根源に迫るかつてない組織論。軍事的手段としての軍の価値は、「戦闘力」×装備の質と量となる。戦闘力は精神的、知的、組織的な基盤に依拠し、規律と団結力、士気と主導権、勇猛さと頑強さ、戦闘意欲と必要ならば死ぬ覚悟といったものを様々に組み合わせた形で体現される。何が戦闘力を生み出しているのか。『戦争の変遷』『補給戦』などで著名なクレフェルト教授が、賞賛に値する水準まで戦闘力を発展させた歴史上の組織である、第二次世界大戦のドイツ陸軍に着目。同時期のアメリカ陸軍と比較して戦闘力の根源に多角的に迫る。
目次
問題の所在
民族性の役割
軍隊と社会
ドクトリンと戦争のイメージ
指揮の原則
陸軍の組織
陸軍の人事行政
戦闘効率の維持
報酬と懲罰
下士官
統率と士官団
結論
著者等紹介
ファン・クレフェルト,マーチン[ファンクレフェルト,マーチン] [van Creveld,Martin]
ヘブライ大学名誉教授。ヘブライ大学歴史学部卒業。ロンドン大学政治経済学院(LSE)博士課程修了(Ph.D.)。専門は戦略研究、軍事史
塚本勝也[ツカモトカツヤ]
防衛省防衛研究所戦史研究センター安全保障政策史研究室長。筑波大学卒業。青山学院大学大学院を経て、フルブライト奨学生としてタフツ大学フレッチャー法律外交大学院留学。同修士、博士課程修了(Ph.D.)。2018~2019年、ダートマス大学米国外交政策・国際安全保障フェロー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
- 洋書
- A New Friend