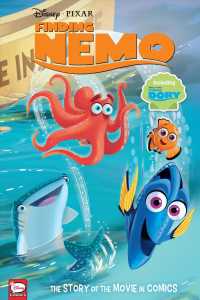- ホーム
- > 和書
- > 理学
- > 環境
- > 資源・エネルギー問題
出版社内容情報
自然エネルギーは、作れば作るほど安くなる“工業製品”だ!
太陽光発電や風力発電による電力は再生可能エネルギー、または自然エネルギーとも言われるが、実は工場で大量生産される“工業製品”でもある。こうした電力は「スワンソンの法則」に沿って、作れば作るほど安くなることが知られている。事実、太陽光発電の発電コストは既に当初の1/100になっている。しかもまだまだ安くなり、その下限は見つからない。将来的には、太陽光発電の発電コストは“ほぼタダ”に近づく。
米フォードが20世紀初頭に自動車を大量生産し、“馬”に頼っていた我々の移動手段を一変させたように、電力の世界もこれまでの化石燃料の“狩猟採集時代”から“工業化時代”へと変わる。すると我々の生活も大きく変わる。今から再エネを積極的に導入していけば早ければ2050年には日本でも現行の電力需要量と同じ量(約1兆キロワット時)を再エネだけで賄える計算で、電気料金は現行の1/10~1/2になる。製造業はもちろん、物流、運輸、情報通信などに掛かっていた諸費用も大幅に安くなる。空飛ぶタクシーなどの新産業にとっても朗報だ。石油あるいは石油から作られていた化学製品が電気エネルギーを使った合成によって自然エネルギーから作られるようにもなる。
その実現のために、取り組む必要があるのは再エネの大量生産だけではない。その工業製品としての“電力”を一時保管する倉庫、つまり蓄電池も大量生産する必要がある。電力の工業化時代は、蓄電池が社会の隅々まで浸透した“蓄電池社会”でもある。その先には“水素社会”も待っている。
内容説明
電気料金が高止まりしている原因は燃料の狩猟採集と社会主義的システムにあった!?太陽電池、蓄電池、燃料電池の「電池3兄弟」が“電力の産業革命”を生み出す。通信とエネルギー取材歴20年超の記者が語る、目からウロコの技術的興国論。
目次
第1章 なぜ今、電気代を1/10にできないか―格安料金の実現を阻む黒幕(1/10にならない2つの理由;電力系統は最後の超計画経済;黒幕は「同時同量則」)
第2章 太陽電池/再エネ編 再エネの本質は電力の工業化―電力源の“狩猟採集”時代が終焉へ(再エネは工業製品;日本でも再エネが本格化;いきなり洋上風力発電大国に?:送電線問題と同時同量則が最後の壁:送電線容量はルール変更で2倍に)
第3章 蓄電池編 電力を貯められる時代に―“電力の東側陣営”から脱却へ(蓄電池で同時同量則の鎖を断ち切る;リチウムイオン2次電池を大量導入へ;再エネ+蓄電池でコストは見合うのか:次世代電池でさらに低コストに)
第4章 水素/燃料電池編 “運べる電気”が実現―蓄電池との連携でコストの壁を突破(水素/燃料電池も活用へ;クルマから始まる“蓄電池+水素”社会;蓄電池で水素も安くなる:“運べる電気”で送電線増設を回避)
第5章 省エネ技術編 2050年、電気料金1/10の実現へ―その先には再エネ100%社会も可能に(再エネの大量導入は100年続く;電気の無駄遣いを推奨へ?;火力発電も“再エネ”に変身:今後の経済成長は省エネ技術の成長)
著者等紹介
野澤哲生[ノザワテツオ]
早稲田大学理工学部応用物理学科卒。大学院修了後、1998年に日経BPに入社。通信関連の雑誌『日経コミュニケーション』記者、2004年から『日経エレクトロニクス』記者として通信技術、半導体、新材料、高性能コンピューター(HPC)、エネルギー、人工知能(AI)分野の取材を重ねる。2018年4月から『日経クロステック』副編集長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Z
Haruki
kentatnek