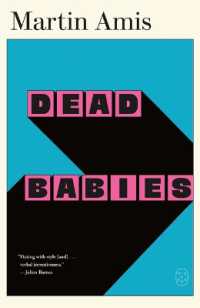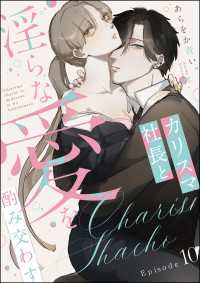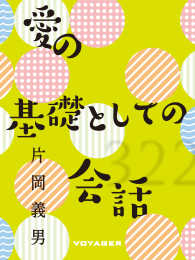出版社内容情報
★優秀な人を集めたのにできあがったのは残念な組織、いったいなぜ?
★集団心理の専門家による「組織」の心理
★働く「みんな」のつくり方を知るために
人は、集団になると愚かな決断をする
集団よりもひとりで働くほうが人間関係でもめないし、同調圧力に屈することもないし、サボる人も少ないでしょう。
しかし、やはり大きな仕事は集団でないと成し遂げられません。
集団には問題がつきものです。「意見を言っただけなのに人間関係が悪くなる」「ものを言える空気がない」などの問題が起きるのは、集団で暮らす人間の特性が背景にあります。人には、「古来より変わらない普遍の集団心理」と「現代特有の集団心理」がありますが、このふたつを押さえて、集団について考える必要があります。組織を一歩進めたいとき、「集団心理」を知ることはとても有効です。 この本は、社会心理学、産業・組織心理学の専門家が、どのように集団をよくしていくかを科学的な知識や論文を背景に、さまざまにご紹介します。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メタボン
21
☆☆☆ 集団心理学による職場の組織論。協力的環境では批判が創造性を高めるが競争的環境では逆に低める。チームに必要な4つの要素「目標の共有」「相互協力」「役割分担」「成員の認識」。変革型リーダーシップ「理想的影響」「モチベーションの鼓舞」「知的刺激」「個別配慮」。真のリーダーは奉仕者である。表面上の主張にとらわれていても対立の解消は難しく、その背後にあるニーズを見極めることが対立解消のカギ。2025/05/30
きんばら いつき
15
多様性にしろ、テレワークにしろ、チームのパフォーマンスにとって一概によい悪いと言えないのは心に留めておきたい。単純に「これはよい(悪い)もの」と認識するのは楽だが、複数の作用があり、プラスとマイナスの双方に働くというのは言われてみれば当たり前。ただ、つい単純なラベリングをしてしまう。また、「みんなでみんなを勘違い」の多元的無知は興味深い。拍手しているからといって、内心でも賛成とは限らないのに「みんな拍手しているから…」とつられて拍手をしてしまう。実は積極的な賛成は少数でも、熱狂的な全会一致に見えるのは怖い2025/07/25
PAO
10
覚えておきたい事柄や単語が沢山あったので備忘的に記します。「集団だからうまくいかない」「集団浅慮」「集団規範と同調」「社会的手抜き」「烏合の衆をチームに変える」「リーダーシップとは」「メンバーの対立」「心理的安全性」「多様性」「テレワークとバーチャルチーム」…個人的にはテレワークにより対面による顔色をうかがうことや周囲にも気を使う必要が無くなったのでコミュニケーション効率は以前より向上したと思っています。少なくとも従来の様な職場環境は通用せず変えていかなければならなくなったと考えたいです。 2025/11/01
ソーシャ
7
集団思考や多元的無知、心理的安全性など組織心理学のホットトピックを社会人向けにわかりやすくかつ実践的に解説した一冊。研究者だけあって具体的な事例や研究の内容も紹介されているのに加えて、産業・組織心理学の基本的な考え方もわかりやすく解説されているのがありがたいです。わかりやすい図や絵が多く使われていて、忙しい人でも読みやすい配慮もなされています。2025/03/30
spike
6
こういう本を読む時は誰でも(リーダーシップを取る立場であってもそうでなくても)、自分が所属する組織の課題を頭に思い描きながら読むのだと思う。同じように読み進めていたのだが、どんどん課題と限界がすぐ思い浮かんでしまって辛いものがあった。それだけこの本はわかりやすいし読みながらいろいろすぐにイメージしたり思考できる、ということでもある。本のデザインからイメージするよりもかなり良書だと思う。2025/06/05