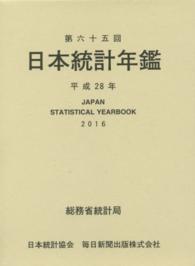内容説明
写真を撮ること、表現することの可能性。全クリエイターが持つべき知恵と勇気。あらゆるクリエイティブが一瞬で消費される時代に表現を続けていく意味を写真家、文学研究者と渡り歩いてきた著者が体験とともに解き明かす。
目次
序章 写真とは何か(写真に真実は写るのか;写真における真実とは何か ほか)
1章 撮ることと世界の認知(世界を認知するということ;写真と嘘と事実と真実 ほか)
2章 表現することの価値(表現のコモディティ化;写真という「語り直し」の産物 ほか)
3章 写真で何を語るのか(全人類総写真家時代の幕開け;ストゥディウムとコモディティ ほか)
著者等紹介
別所隆弘[ベッショタカヒロ]
フォトグラファー、文学研究者、ライター。関西大学社会学部メディア専攻講師。毎日広告デザイン賞最高賞や、National Geographic社主催の世界最大級のフォトコンテストであるNature Photographer of the Year “Aerials”2位など、国内外での表彰多数。写真と文学という2つの領域を横断しつつ、「その間」の表現を探究している。滋賀、京都を中心とした“Around the Lake”というテーマでの撮影がライフワーク(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。