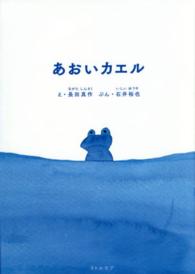内容説明
万葉時代から平安時代にかけて和歌が洗練されていく過程は、人間の精神性の高まりの過程でもあった。その過程を探り、自然環境保護と日本文化継承との切り離せない関係を考察していく。「ころころ」は「こころ」の古代語。日本では、大昔から「こころ」は「コロコロ」した球形だと考えられてきた。そのような日本人的感覚により生み出される調和と循環の世界を、「若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る」(万葉集・山部赤人)で有名な「和歌の浦」の失われた景観の復元と、和歌にみられる日本人の自然観の重要性からひもとく書。
目次
序文(研究目的と方法(11次元論法)
日本の自然と和歌
歌枕「和歌の浦」を題材とした理由)
第1章 「和歌の浦」の景観の復元―私たちの身近な地域を見直す(「万葉集」にみられる万葉びとの自然と宗教意識;歌枕となった万葉の「和歌の浦」とは;和歌に詠まれた「和歌の浦」)
第2章 日本人の表現の原点である和歌―和歌表現からみてとれる自然の多次元性(「万葉集」から「新古今集」に至る歌枕の史的変容;平安和歌の達成;和歌を起源とする日本文学)
第3章 地球の自然環境破壊の現状と方向性―日本人の自然観に学ぶこと(「和歌の浦」の失われた景観と開発の実態;世界規模の自然環境破壊;日本人的感覚により生み出される調和と循環の世界)
むすび 自然と人間の共存
著者等紹介
木下直子[キノシタナオコ]
1967年和歌山市生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。子供達の未来のために、後世へ受け継いでいくことの大切さを実感し、日本文化継承、環境保全、人間教育を3つの柱として、「日本文化の善さ」を広める活動をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。